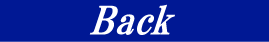●定例会を終わって ●主な質問・質疑 ●会期日程 ●本会議一般質問 ●予算総括質疑 ●意見書・決議 ●議員提案条例
離島・半島地域の振興対策に関する意見書
離島・半島地域は、豊かな自然と独自の歴史・文化を有し、食料の安定的な供給、国土や自然環境の保全など国民の利益を増進する重要な役割を担っている。
加えて、近年の田園回帰志向の高まりや働き方改革の流れの中、豊かな自然環境や文化資源を有する離島・半島地域は、都市住民に対して魅力的な余暇生活、移住・定住や二地域居住の場を提供できる地域である。
特定有人国境離島地域においては、平成29年4月の「有人国境離島法」の施行を受け、雇用機会の拡充、航路・航空路の運賃低廉化、滞在型観光の促進等に取り組んだ結果、雇用の創出や交流人口の拡大に結びつくなど、人口の社会減の抑制が図られているところであるが、これを一過性とすることなく、継続し、定着させていくことが必要である。
また、半島地域においても、産業や生活を支える道路・港湾などの社会基盤整備が着実に進められ、産業振興、移住・定住促進対策などの施策の推進に結びついており、継続した取組が必要である。
このような中、離島・半島地域を有する15市町の移住施策については、移住者数が平成28年度に417人、平成29年度に731人、平成30年度も12月末現在で703人となるなど、着実な成果に結びついているところである。
さらに、平成30年7月に「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産」が世界文化遺産として登録されたところであるが、その多くが長崎の離島・半島地域に点在しており、観光や産業振興に更なる活用が期待される。
よって、県におかれては、下記の事項について、積極的かつ真摯に取り組まれるよう、強く要望する。
記
- 離島・半島地域振興対策について
- (1)離島・半島地域において重要な役割を果たしてきた一次産業を今後も維持・発展させていくために、各地域の特産品のブランド化や、それぞれの特色を生かした産地づくりに努めること。
- (2)企業誘致、移住及び若者定着に関するそれぞれの情報を庁内担当部局間で共有するとともに、より大きな相乗効果を生み出すよう、関係施策を連携して推進すること。
- (3)企業誘致に際しては、都市部の企業のサテライトオフィス等の誘致を推進すること。
- (4)人材確保が難しい離島・半島地域の医療・介護分野でこそIT化が重要であることを認識し、各事業者への導入支援等の取組を進めること。
- (5)しまの看護師確保対策として各看護学校へ看護情報誌を配布しているところであるが、高等学校等にも配布するなど、看護師を志す学生が増えるような取組にも努めること。
- (6)本県の代表的な温泉地である雲仙・小浜は、平成28年の熊本地震以降、他県の温泉地と比べ集客の回復が遅れている。別府や由布院等、同じ九州でありながら現に回復し、好調な温泉地を分析するとともに、観光県「長崎」であることを認識したうえで、観光関係者と連携して集客回復に全力を尽くすこと。また、一般社団法人島原半島観光連盟が実施している旅行者アンケートの調査結果を分析し、今後の半島地域の観光振興策に反映させること。
- (7)離島航路において、観光客の延泊費用を補償する欠航補償制度が今年度導入され、旅行者の安心感に寄与しているところであるが、これを一過性とすることなく、来年度以降も継続して実施されるよう予算確保及びPR等に最大限努めること。
- 有人国境離島法対策について
- (1)雇用機会拡充事業については、若者の島外流出の抑制に効果的な新規高校卒業者の雇用にもつながるよう必要な対策を講じること。また、島外、特に県外からの事業者をさらに引き込むため、情報収集や掘り起こし、各市町との情報共有等に努めること。
- (2)地域商社のストック機能を持つ本土の物流拠点整備については、各地域商社や専門業者の意見を取り入れ、スピード感を持って、機能的な仕組みづくりに努めること。
- (3)各地域商社の組織体制については、人材の育成及び民間人材の活用が重要であるため、県においても積極的に支援すること。また、地域商社の販路拡大についても、各地域商社にまたがる横断的な分野を中心に、県も主体性を持って取り組むこと。
- (4)本県観光の大きな特徴の1つである修学旅行が「しま旅滞在促進事業」の対象となったところであるが、修学旅行客の増加につながるよう関係市町と連携して施策を立案し、制度拡充に向けて国へ要望を行うこと。
- (5)航路・航空路の運賃低廉化に関しては、市町等の意見も取り入れながら、準住民の適用範囲の拡大等について国へ要望を行うこと。
以上、意見書を提出する。
平成31年2月20日
長 崎 県 議 会
(提出先)
長崎県知事 中村 法道 様
長崎県の観光振興の促進に関する意見書
世界全体の国際観光客数は近年増加し続け、2030年には18億人になると予測されている。わが国の観光立国に向けた取組も成果が現れつつあり、2018年には訪日客数が3,000万人を超え、過去最高を記録した。
一方で、訪日客の多くは大都市圏及び特定有名観光地等に集中している。今後、観光の特定地域への偏りを是正すべく地域分散型を推進し、併せて交流人口の拡大を図り、全国各地に訪日客増加の効果を波及させていくことが、地方創生の観点からも重要である。
本県においては、豊富な観光資源を十分に活用しつつ、ラグビーワールドカップ2019や女子ハンドボール世界選手権大会、東京2020オリンピック・パラリンピックをはじめとする大規模イベントの開催を好機として捉え、ゴールデンルートからの積極的な誘客を図り、基幹産業である観光業の成長に繋げることが出来れば、県内経済の発展の基盤を築くことが可能となる。
よって、県におかれては、成長し続ける世界の観光市場を取り込み、「観光県長崎」の更なるブランドの確立に向けた取組を拡充するとともに、次の事項について適切な措置を講じるよう強く要望する。
記
- 観光振興について
- 2015年の「明治日本の産業革命遺産」の世界文化遺産登録に続き、2018年7月に「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産」が世界文化遺産に登録され、これを機に多くの観光客が本県を訪れている。年齢や身体の不自由さに関係なく、より多くの方に本県の歴史や文化、食の魅力を体験していただき、リピーターの創出に繋がるように下記の対策に努めること。
○高齢者や障害者等を含め、より多くの方が世界文化遺産を訪れることが可能となるようなバリアフリー対策
- 国際戦略(東南アジア)について
- 効果的なインバウンド・アウトバウンド促進のためには、各国の消費者の嗜好や市場の特性を踏まえた戦略が重要である。特に経済成長が著しいアジア諸国への戦略について確認するとともに、アジア諸国の経済成長の効果を取り込むために体制の整備に注力する必要があるため下記の対策に努めること。
○個人旅行客等の誘致拡大のための推進体制の整備
○県産品の輸出を専門的に扱う推進体制の整備
○県内企業の海外展開における、ジェトロ等の輸出促進関係団体との協力体制の整備
- IR対策について
- 統合型リゾート(IR)は、観光及び地域経済の振興に大きく寄与し、雇用の創出も見込まれる。本県にとっては、IR誘致は千載一遇の好機であるため、県内はもとより
九州地区の気運をより一層高め、全力で取り組む必要がある。一方で、カジノ施設が地域住民に不安をもたらさないように綿密な計画性を持って取り組むことが求められる。
このことを踏まえて、本県のIR区域認定に向けて下記の対策に努めること。
○ギャンブル依存症対策
○IR誘致に向けての県組織の推進体制の強化
- 長崎空港対策について
- 近年LCCの参入により訪日客の増大や国内観光が拡大している。観光振興にとって長崎空港の担う役割は大きく、国内線はもとより、国際線も新規路線の拡充を図り交流人口を増やすことが望まれている。そのためには、利用者・航空事業者両者の利便性や効率性を高める必要があるため下記の対策に努めること。
○国内航空路線における他の24時間空港との相互運航による空港運用時間の延長
以上、意見書を提出する。
平成31年2月20日
長 崎 県 議 会
(提出先)
長崎県知事 中村 法道 様
総合交通対策に関する意見書
地域公共交通は、まちづくりや観光、健康、福祉など様々な分野に効果を及ぼすものであり、地域の存続・活性化のためには移動手段の確保が必要不可欠である。
しかしながら、全国的に人口減少・少子高齢化が進む中、公共交通利用者も地方部を中心に減少しており、日々の暮らしを支える鉄道やバス路線、航路、航空路などを維持することが困難な状況となっている。
また、高齢ドライバーによる相次ぐ重大交通事故の発生や改正道路交通法の施行を背景に、運転免許返納者への地域公共交通の確保等、社会全体で高齢者の生活を支える体制の整備が求められるとともに、公共交通空白地域の住民や高齢者等交通弱者の外出の機会を増やし、生きがいや健康づくりにつなげるため、移動手段の確保は重要な課題である。
離島を多く有する本県では、全国を上回るスピードで人口減少が進んでおり、離島住民の大切な移動手段を維持し、有人国境離島法を活用した交流人口の拡大を図るためにも、離島航路・航空路を維持・拡充する必要がある。併せて、半島地域における鉄道やバス路線、航路についても、住民生活や交流の活性化のため、地域と連携して支えていかなければならない。
このような中、昨年10月に起きた株式会社五島産業汽船の突然の全航路運休については、離島住民や観光客等の移動に多大な影響を与え、離島航路を維持する重要性について改めて認識させられたところである。
さらに、「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産」の世界文化遺産登録等による国内外からの観光客の増加や九州新幹線西九州ルートの開業を控え、主要な空港・港・駅からの2次交通を整備・改善していくことも重要である。
よって、県におかれては、下記の事項について、積極的かつ真摯に取り組まれるよう、強く要望する。
記
- 離島地域航路・航空路対策について
- (1)国や関係航空会社で構成される「地域航空の担い手のあり方に係る実務者協議会」の検討結果などを踏まえながら、持続可能な地域航空の実現に向けて、オリエンタルエアブリッジ(ORC)と十分な連携のもと、機材の更新等を推進すること。
- (2)離島航路の維持・確保のため、船舶の円滑な更新ができるよう取り組むとともに、国・市町・事業者と連携を密にして安定的な運航を図り、利便性の向上に努めること。また、安定的な運航を図るための手法として、共同運航についても研究・検討を行うこと。
- (3)離島地域の交流人口を増加させる観点から、未利用空港を含めた離島空港の利用促進を図ること。
- 地域・2次交通対策について
- (1)交通系ICカードについては、利用者にとって利便性が高まるよう交通事業者と連携して取り組むこと。
- (2)地域公共交通の維持のため、市町の状況の把握に努め、コミュニティバスや乗り合い・デマンドタクシーなど多様な交通手段の展開を推進すること。
- (3)路線バス事業等にかかる運転士確保が難しい中、地域交通維持に向けて、人材確保対策を推進すること。
- (4)地域鉄道については、地域住民及び地域活性化のための大切な交通手段であることから、引き続き施設整備等に係る支援を図ること。
- (5)県営交通事業について、地域住民の利便性が高まるよう、市町や民間交通事業者等と連携・協力しながら交通施策を推進すること。
- (6)九州新幹線西九州ルートの整備にあたっては、県民に新幹線の整備効果に対する理解の促進が図られるよう努めること。また、新幹線駅から魅力ある資源を有する県内各地への2次交通を整備・改善し、新幹線の開業効果を高めるよう努めること。
- (7)「長崎と天草地方の潜伏キリシタン関連遺産」の世界文化遺産登録による国内外の観光客の増加に対応するため、長崎県内と天草間の交通アクセスについて、国・市町・事業者と連携した対応に努めること。
- 医療・福祉・高齢者等交通弱者対策について
- (1)介護サービスにおける移送対策について、市町と連携を図りながら、地域での充実が図られるよう努めること。
- (2)高齢者や障害者等が安心して生活できるよう、市町や事業者等と連携して、バリアフリーの現状把握に努め、交通環境の整備を図ること。
- (3)運転免許自主返納高齢者等について、各地域の特性・実情に応じ、公共交通利用等の支援策が講じられるよう努めること。
以上、意見書を提出する。
平成31年2月20日
長 崎 県 議 会
(提出先)
長崎県知事 中村 法道 様
九州新幹線西九州ルートの整備促進に関する意見書
九州新幹線西九州ルートは、西九州地域の産業振興や交流人口の拡大等につながる、重要な交通基盤であり、関西圏・中国圏との連携による社会経済の発展に寄与するものである。また、沿線地域では、官民が一体となって新幹線の効果を最大限に発揮できるよう、ソフト・ハード両面から新幹線を活用した魅力あるまちづくりに懸命に取り組んでいる。
この西九州ルートについては、フリーゲージトレイン(FGT)が山陽新幹線へ乗り入れるという前提であったが、与党整備新幹線建設推進プロジェクトチーム「九州新幹線(西九州ルート)検討委員会」において、高速化の進む山陽新幹線への乗り入れは困難であることから、西九州ルートへの導入は断念せざるを得ないとされている。
今後の整備のあり方について、同検討委員会において、フル規格又はミニ新幹線のいずれかを選択するとされているが、ミニ新幹線については、工事期間中に輸送力が低下することや輸送障害の発生によりダイヤの安定性が劣ることなどの課題がある。
一方、フル規格については、国土交通省が平成30年3月に示した試算結果で高い整備効果が示され、本県としてもこの結果を高く評価しており、フル規格により整備することこそ西九州地域の発展に最も寄与することをあらためて確認している。
よって、県におかれては、西九州ルートの全線フル規格による整備を実現するため下記の事項について政府・与党等へ強く働きかけるよう求める。
記
- 国の責任において早急に議論を進め、整備のあり方については、課題の残るミニ新幹線ではなく、投資効果・収支改善効果・時間短縮効果が最も高い、フル規格による整備方針を早期に決定すること。
併せて、西九州ルートへの直通運行も視野に入れたJR佐世保線の輸送改善に向けた支援の充実を図ること。 - 整備新幹線建設に伴う地方公共団体の建設費負担については、国が開発を進めてきたFGTの導入が困難になったという特殊事情も考慮し、国の責任において地方負担の軽減に向けて抜本的な対策を講じること。
- 建設中の武雄温泉~長崎間の建設費の増額については、厳しい財政状況の中、過度の追加負担が生じないようコスト縮減や十分な財政措置を講じること。
以上、意見書を提出する。
平成31年2月20日
長 崎 県 議 会
(提出先)
長崎県知事 中村 法道 様
放課後児童クラブの質の確保を求める意見書
放課後児童クラブでは、就労等により保護者が昼間家庭にいない子どもを対象として、放課後等に学校の余裕教室等や専用施設等で適切な遊びや生活の場を提供することにより、安全安心な環境の下、その健全な育成を図っている。
女性の就労拡大等に伴い、放課後児童クラブの利用児童数は年々増え続けており、子どもが安全に安心して放課後を過ごせる放課後児童クラブのニーズはますます高まっており、その目的・役割を果たすためには、放課後児童クラブの質の確保が求められ、放課後児童支援員については研修等による資質の向上が必要不可欠である。
そのため、国が策定した「放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準」に基づき市町村が条例を定める際、職員の配置基準については従うべき基準とされているところである。
今般、従うべき基準を参酌化するという閣議決定がなされたところであるが、もし職員配置基準が緩和されれば、場合によっては、資格を有しない者が1人で多くの児童を受け持つという状態が生じ、子どもの安全安心が保障されないことが懸念される。
よって、国におかれては、「放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準」の従うべき基準を参酌化しても、市町村が質の確保を担保するよう、都道府県は安全・安心が確保できない体制は認めないよう働きかけを行うことを強く求める。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成31年 3月15日
長 崎 県 議 会
(提出先)
衆議院議長 大島 理森 様
参議院議長 伊達 忠一 様
内閣総理大臣 安倍 晋三 様
財務大臣 麻生 太郎 様
経済産業大臣 世耕 弘成 様
厚生労働大臣 根本 匠 様
内閣府特命担当大臣(少子化対策)宮腰 光寛 様
内閣府特命担当大臣(地方創生) 片山 さつき様
食品ロス削減に向けてのさらなる取り組みを進める意見書
まだ食べることができる食品が、生産、製造、販売、消費の各段階で廃棄されている、いわゆる食品ロスの削減は、今や我が国において喫緊の課題と言える。国内で発生する食品ロスの量は年間646万トン(2015年度)と推計されており、これは国連の世界食糧計画(WFP)が発展途上国に食糧を援助する量の約2倍に上る。政府は、国連の「持続可能な開発目標(SDGs)」に沿い、家庭での食品ロスの量を2030年度までに半減させることを目指しているが、事業者を含め国民各層の食品ロスに対する取り組みや意識啓発が必要不可欠である。
食品ロスを削減していくためには、国民一人一人が各々の立場において主体的にこの課題に取り組み、社会全体として対応していくよう、食べ物を無駄にしない意識の醸成とその定着を図っていくことが重要である。
また、まだ食べることが出来る食品については、廃棄することなく、貧困、災害等により必要な食べ物を十分に入手することができない人に提供するなど、できるだけ食品として活用していくことが重要である。
よって、国におかれては、国、地方公共団体、事業者、消費者等が一体となって食品ロス削減に向けての取り組みを進めるため、下記の事項について真摯に取り組むことを強く求める。
記
- 国、地方公共団体、事業者、消費者等の多様な主体が連携し、食品ロスの削減を総合的に推進するため、法律の制定を含めたより一層の取り組みを実施すること。
- 商慣習の見直し等による食品事業者の廃棄抑制や消費者への普及・啓発、学校等における食育・環境教育の実施など、食品ロス削減に向けての国民運動をこれまで以上に強化すること。
- 賞味期限内の未利用食品や備蓄品等を必要とする人に届けるフードバンクなどの取り組みをさらに支援すること。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。
平成31年 3月15日
長 崎 県 議 会
(提出先)
衆議院議長 大島 理森 様
参議院議長 伊達 忠一 様
内閣総理大臣 安倍 晋三 様
環境大臣 原田 義昭 様
文部科学大臣 柴山 昌彦 様
厚生労働大臣 根本 匠 様
農林水産大臣 吉川 貴盛 様
経済産業大臣 世耕 弘成 様
内閣府特命担当大臣 宮腰 光寛 様
(消費者及び食品安全)
内閣官房長官 菅 義偉 様