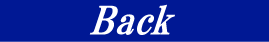意見書・決議
国営諫早湾干拓事業の潮受堤防排水門の開門に対する意見書
去る6月27日に、諫早湾干拓事業の潮受堤防撤去および常時開門等を求める「工事差し止め等請求事件」において、「判決確定の日から3年を経過する日までに、防災上やむを得ない場合を除き、北部および南部排水門を開放し、以後5年間にわたって同排水門の開放を継続せよ」という判決が佐賀地裁で出された。
また、判決の中で、排水門の常時開放を前提として「結局代替することができないため、支障が生じる7年間程度の農業生産についても、予備的請求に係る原告らの漁業行使権の侵害に対して、優越する公共性ないし公益上の必要性があるとは言い難い」とされているが、当判決は、洪水に悩まされ続けた地元住民の感情や環境保全型農業の実現に向けて懸命に取組んでいる農業者の方々の実態を全く無視した内容であると言わざるを得ない。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 平成20年7月4日 |
長 崎 県 議 会 |
(提出先) 内閣総理大臣 農林水産大臣 環境大臣 内閣官房長官 衆議院議長 参議院議長 |
福田 若林 鴨下 町村 河野 江田 |
康夫 正俊 一郎 信孝 洋平 五月 |
様 様 様 様 様 様 |
燃油価格高騰に伴う農林水産業に係る緊急対策を求める意見書
本県は、全国に比べて第一次産業の就業者の割合が高く、特に離島・半島においては地域全体を支える重要な基幹産業となっている。 記
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 平成20年7月11日 |
長 崎 県 議 会 |
(提出先) 内閣総理大臣 財務大臣 農林水産大臣 経済産業大臣 内閣官房長官 衆議院議長 参議院議長 |
福田 額賀 若林 甘利 町村 河野 江田 |
康夫 福志郎 正俊 明 信孝 洋平 五月 |
様 様 様 様 様 様 様 |
国営諫早湾干拓事業に関する今回の大臣談話に対する意見書
|
去る6月27日に、佐賀地方裁判所において下された、諫早湾干拓事業に係る「工事差し止め等請求事件」の判決に対して、国では、7月10日に控訴した。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 平成20年7月14日 |
長 崎 県 議 会 |
(提出先) 内閣総理大臣 農林水産大臣 環境大臣 内閣官房長官 衆議院議長 参議院議長 |
福田 若林 鴨下 町村 河野 江田 |
康夫 正俊 一郎 信孝 洋平 五月 |
様 様 様 様 様 様 |
地方税財源の充実・強化に関する意見書
地方公共団体が自主性・自立性を高め、地域の実情に応じた公共サービスを提供するためには、地域間の格差を調整し、必要な財源が保障されることが重要であり、地方税財源の充実・強化が不可欠である。 記
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 平成20年7月25日 |
長 崎 県 議 会 |
(提出先) 内閣総理大臣 総務大臣 財務大臣 内閣官房長官 衆議院議長 参議院議長 |
福田 増田 額賀 町村 河野 江田 |
康夫 寛也 福志郎 信孝 洋平 五月 |
様 様 様 様 様 様 |
義務教育にかかる確実な財源保障と制度の堅持を求める意見書
義務教育費国庫負担制度については、教育の機会均等とその水準の維持向上を確保するうえで、極めて重要かつ根幹的な制度であり、これまで国は、地方が義務教育にかかる共同責任を果たせるよう、財政的に下支えしてきたところである。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 平成20年7月25日 |
長 崎 県 議 会 |
(提出先) 内閣総理大臣 総務大臣 財務大臣 文部科学大臣 内閣官房長官 衆議院議長 参議院議長 |
福田 増田 額賀 渡海 町村 河野 江田 |
康夫 寛也 福志郎 紀三朗 信孝 洋平 五月 |
様 様 様 様 様 様 様 |
真に国民のための医療を実現する「社会保障費削減撤廃」を求める意見書
我が国の医療保険制度は、誰でも、いつでも、どこの医療機関でも受診ができる国民皆保険制度のもと、世界最高水準の平均寿命や高い保健医療水準を実現してきた。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 平成20年7月25日 |
長 崎 県 議 会 |
(提出先) 内閣総理大臣 厚生労働大臣 内閣官房長官 衆議院議長 参議院議長 |
福田 舛添 町村 河野 江田 |
康夫 要一 信孝 洋平 五月 |
様 様 様 様 様 |
長寿医療制度(後期高齢者医療制度)の改善を求める意見書
平成18年6月の健康保険法等の一部を改正する法律により、75歳以上の高齢者等を対象とした長寿医療制度(後期高齢者医療制度)が、本年4月1日から実施された。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 平成20年7月25日 |
長 崎 県 議 会 |
(提出先) 内閣総理大臣 厚生労働大臣 内閣官房長官 衆議院議長 参議院議長 |
福田 舛添 町村 河野 江田 |
康夫 要一 信孝 洋平 五月 |
様 様 様 様 様 |
安心できる地域医療体制の確保を求める意見書
現在、全国的に勤務医不足が顕著になっており、とりわけ小児科・産科医不足に見られる専門性、地域性の偏在解消が喫緊の課題となっている。 記
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 平成20年7月25日 |
長 崎 県 議 会 |
(提出先) 内閣総理大臣 総務大臣 財務大臣 厚生労働大臣 内閣官房長官 衆議院議長 参議院議長 |
福田 増田 額賀 舛添 町村 河野 江田 |
康夫 寛也 福志郎 要一 信孝 洋平 五月 |
様 様 様 様 様 様 様 |
森林・林業・木材産業施策の積極的な展開を求める意見書
地球温暖化が深刻な環境問題となる中で、近年、森林の役割に対する要請が高まるなど、環境資源としての森林に対し強い期待が寄せられている。 記
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 平成20年7月25日 |
長 崎 県 議 会 |
(提出先) 内閣総理大臣 財務大臣 農林水産大臣 経済産業大臣 環境大臣 内閣官房長官 衆議院議長 参議院議長 |
福田 額賀 若林 甘利 鴨下 町村 河野 江田 |
康夫 福志郎 正俊 明 一郎 信孝 洋平 五月 |
様 様 様 様 様 様 様 様 |
道路整備の安定的な財源確保を求める意見書
本県は国土の西端に位置し、離島・半島が多いこともあり、骨格である高規格幹線道路や地域高規格道路の整備が未だに不十分であり、地域格差の解消や地方の自立を図るためには、企業立地や観光振興等を支援する道路網の整備が極めて重要である。また、交通渋滞の緩和や暮らしの安全・安心の観点から、生活幹線道路の整備も必要であり、道路整備に対する県民の要望は非常に強く、これらの道路整備を計画的に進めるためには、それに見合った財源確保が不可欠である。 記
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 平成20年7月25日 |
長 崎 県 議 会 |
(提出先) 内閣総理大臣 総務大臣 財務大臣 国土交通大臣 経済財政政策担当大臣 内閣官房長官 衆議院議長 参議院議長 |
福田 増田 額賀 冬柴 大田 町村 河野 江田 |
康夫 寛也 福志郎 鐵三 弘子 信孝 洋平 五月 |
様 様 様 様 様 様 様 様 |
拉致問題の早期解決を求める意見書
北朝鮮による拉致は、我が国の国家主権及び国民の生命と安全に関わる重大な問題であり、未曾有の国家的犯罪である。我が国は、すべての拉致被害者の安全を確保し、直ちに帰国させるとともに、拉致に関する真相の究明と拉致実行犯の引渡しを強く要求している。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 平成20年7月25日 |
長 崎 県 議 会 |
(提出先) 内閣総理大臣 外務大臣 内閣官房長官 衆議院議長 参議院議長 |
福田 高村 町村 河野 江田 |
康夫 正彦 信孝 洋平 五月 |
様 様 様 様 様 |