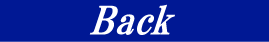意見書・決議
義務教育にかかる確実な財源保障と制度の堅持を求める意見書
|
義務教育費国庫負担制度については、教育の機会均等とその水準の維持向上を確保するうえで、極めて重要かつ根幹的な制度であり、これまで国は、地方が義務教育にかかる共同責任を果たせるよう、財政的に下支えしてきたところである。 義務教育費国庫負担制度の改革については、平成17年11月の政府・与党合意の「三位一体の改革」において、義務教育制度については、その根幹を維持し、義務教育費国庫負担制度を堅持することとされ、費用負担については、国庫負担割合は引き下げられたものの、税源移譲を含め確実に実施する旨の基本方針が決定されたところである。 全国どこにおいても教育水準の維持向上や機会均等を確保することは、言うまでもなく、国が自らの責務としてその役割を果たすべきものであり、各自治体の財政事情により義務教育に格差が生じるようなことがあってはならない。 よって、国におかれては、憲法で定められた教育の機会均等とその水準の維持向上を確保するため、義務教育にかかる財源措置が将来にわたり確実に実施されるよう強く要望する。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 平成19年7月3日 |
長崎県議会 |
(提出先) 内閣総理大臣 総務大臣 財務大臣 文部科学大臣 内閣官房長官 衆議院議長 参議院議長 |
安倍 菅 尾身 伊吹 塩崎 河野 扇 |
晋三 義偉 幸次 文明 恭久 洋平 千景 |
様 様 様 様 様 様 様 |
真に国民のための医療を実現する「医療制度改革」を求める意見書
|
我が国の医療保険制度は、誰でも、いつでも、どこの医療機関でも受診ができる国民皆保険制度のもと、世界最高水準の平均寿命や高い保健医療水準を実現してきた。 しかし、少子高齢化の急速な進展や厳しい財政状況のもと、患者一部負担の引き上げ、リハビリテーションの日数制限や高齢者の長期入院施設の削減など、様々な医療費の抑制策が行われてきている。 このため、必要な医療や介護を受けることができない、いわゆる医療難民や介護難民が出てくることが危惧されるとともに、産科や小児救急医療などをはじめとした地域医療体制にも歪みが生じるなど、地域医療は崩壊の危機に瀕している。 よって、国においては、国民皆保険制度を堅持し、国民が安心して良質な医療を受けられるよう、患者負担の軽減や医療従事者の不足・偏在の解消を図るとともに適正な医療提供に必要な財源を確保されることを強く要望する。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 平成19年7月3日 |
| 長崎県議会 |
(提出先) 内閣総理大臣 厚生労働大臣 内閣官房長官 衆議院議長 参議院議長 |
安倍 柳澤 塩崎 河野 扇 |
晋三 伯夫 恭久 洋平 千景 |
様 様 様 様 様 |
年金問題の早期解決を求める意見書
|
公的年金は、国民にとって、老後の生活に憂いなく、生涯を安心して暮らすために支えとなる非常に重要な収入である。 ところが、最近になって、社会保険庁の納付記録の管理があまりにもずさんなため、約5千万件にも及ぶ不明年金記録の存在が明らかになった。社会保険庁では、これまでも数々の不祥事が問題になったが、今回の問題によって年金不信は一層高まっている。 この不明年金記録の件数の多さは、これまでの数々の不祥事を鑑みれば、単なる事務処理のミスというよりも、社会保険庁の体質そのものに起因すると言わざるを得ない。 年金問題の解決に当たっては、全国の社会保険事務所や市町村に散在している台帳等のデータを徹底的に収集・照合し、全ての納付記録の調査を行うこと。さらに、年金納付記録情報を加入者に明らかにし、納付記録が消滅してしまった方については、加入者側の証言を最大限に尊重して給付対象とする必要がある。 よって、国におかれては、年金問題について、一人の被害者も残すことなく、早期に解決され、国民の信頼回復に最善を尽くされるよう強く要望する。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 平成19年7月3日 |
長崎県議会 |
(提出先) 内閣総理大臣 総務大臣 厚生労働大臣 内閣官房長官 衆議院議長 参議院議長 |
安倍 菅 柳澤 塩崎 河野 扇 |
晋三 義偉 伯夫 恭久 洋平 千景 |
|
道路整備の安定的な財源確保を求める意見書
|
道路は、国民の日常生活や経済・社会活動を支える最も基礎的かつ重要な社会資本であり、地域経済・産業の持続的発展、豊かな地域社会の実現のためには、その整備充実は欠かせないものである。 本県は、我が国本土の西端に位置し、物流の大半を車に依存しているものの、九州の主要都市や本州とを結ぶ九州横断自動車道のインターチェンジまで1時間以上を要する地域が多く、社会経済活動の活性化や地域産業の振興等に支障を来している。このため、高規格幹線道路の西九州自動車道や地域高規格道路の島原道路、西彼杵道路等による高速交通ネットワークの整備が強く望まれている。 しかしながら、本県は多くの離島と半島で形成されており、地形的な要因からトンネルや橋梁あるいは大型の構造物が多く、道路の整備には多額の費用が必要となり、公共事業費が削減される状況下にあって、真に必要な道路ネットワークを早期に整備することは極めて困難となっている。 こうした中、昨年12月に閣議決定された「道路特定財源の見直しに関する具体策」には、真に必要な道路整備は推進することが盛り込まれているものの、一方では毎年の予算で歳出を上回る税収は一般財源化することが明記された。 道路整備が遅れている本県にあっては、今後とも効率的・効果的な道路整備を計画的に進めていきたいが、現在国で策定されている道路整備の中期的な計画における「真に必要な道路整備」の考え方によっては、本県にとって必要な道路整備が大幅に遅れるのではないかと大変危惧している。 よって、国におかれては、公共交通機関が整っている大都市と本県のように整備が遅れている地方では、道路整備に対する住民の意識に違いがあることを十分に認識し、地方の声や実情に十分配慮した、地方が真に必要としている道路整備が遅れることがないよう、道路整備の安定的な財源確保が図られることを強く要望する。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 平成19年7月3日 |
長崎県議会 |
(提出先) 内閣総理大臣 総務大臣 財務大臣 国土交通大臣 経済財政政策担当大臣 内閣官房長官 衆議院議長 参議院議長 |
安倍 菅 尾身 冬柴 大田 塩崎 河野 扇 |
晋三 義偉 幸次 鐵三 弘子 恭久 洋平 千景 |
|
駐留軍関係離職者等臨時措置法の有効期限延長を求める意見書
|
駐留軍離職者対策に大きな役割を果たす「駐留軍関係離職者等臨時措置法」は、平成20年5月16日付で、法期限を迎えることとなる。 改めて申し上げるまでもなく、駐留軍労働者は他国における軍事情勢の変化による極東米軍の動向・政治・政策の変更と併せ、基地の整理・統合等によって直接影響を受ける立場におかれている。また、在日米軍の国内再編に関連して沖縄を中心に大規模基地再編が具体化されるなど、駐留軍関係雇用をとりまく最近の情勢は一段と厳しさを増していることからも「臨時措置法」の法期限の延長の措置は絶対に必要であると考える。 米軍の世界戦略はイラク戦争の長期化と財政支出の増大に加え、北朝鮮をはじめとする新たな核保有国への対応を迫られる等厳しい状況に直面しているため常に変革を余儀なくされている状況にあり、更なる在日米軍の再編の可能性を考えた場合、他の在日米軍部隊への波及等駐労雇用に与える影響は必至であることから駐留軍労働者は大きな不安と危惧を払拭することはできない。 国内的には都市部と地方の格差が拡大し、基地を抱える地方でも景気回復は一向に見られない。離職後の再就職については、池島炭鉱閉鎖時に離職者対策の難しさを痛感しているところであり、現在における再就職環境は極めて厳しいものがある。また、基地を抱える地方の経済に与えるダメージも深刻であり、離職者対策を迫られる自治体にとっても切実な問題である。 よって、国におかれては、「駐留軍関係離職者等臨時措置法」の有効期限延長が図られるよう強く要望する。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 平成19年7月3日 |
長崎県議会 |
(提出先) 内閣総理大臣 外務大臣 防衛大臣 内閣官房長官 衆議院議長 参議院議長 |
安倍 麻生 久間 塩崎 河野 扇 |
晋三 太郎 章生 恭久 洋平 千景 |
|
久間防衛大臣の発言に抗議する決議
|
久間防衛大臣が、去る6月30日、千葉県内の大学における講演会で「原爆投下で戦争が終わった」と言い、原爆投下を是認したかのような発言をされたことは、誠に遺憾である。 被爆後62年を迎える今日においても、なお、多くの被爆者の方々が後遺症に苦しんでいる現状や、これらの被爆者、御遺族の方々に思いをいたすと、不用意な発言と言わざるを得ない。 原爆は、無差別大量殺りくを目的とした非人道的な兵器で、国際法に違反する行為であることは、1996年国際司法裁判所で勧告が出されている。 本県議会は、被爆県として、核兵器の廃絶並びに世界恒久平和に向けて、最大限の努力を払っているところであり、今回の発言を到底容認することができず、厳重に抗議するものである。 以上、決議する。 平成19年7月3日 |
長崎県議会 |