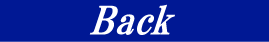定例会等の開催概要
主な質問・質疑
●定例会を終わって ●主な質問・質疑 ●会期日程 ●本会議一般質問 ●予算総括質疑 ●意見書・決議
各常任委員会の委員長報告要旨については、こちらをクリックしてください。
![]()
<審査案件>
議案:第104号議案「長崎県営土地改良事業分担金徴収条例の一部を改正する条例」ほか1件
請願:第1号請願「『事業主報酬制度の早期実現』と『個人企業における事業承継税制の創設』に関する請願書」
<審査結果>
議案:原案のとおり可決すべきものと決定
請願:異議なく採択すべきものと決定
| 議案にかかる主な論議 | |
|---|---|
(質問) |
第106号議案「契約の締結の一部変更について」は、部材の変更が理由であるが、当初設計の際にできなかったのはなぜか。 |
(答弁) |
鋼製の浮防波堤であるが、施工例が少なく変更の技術については、発注者である県にもコンサルにも知識がなかった。発注後、技術提案を受け、情報を収集した結果、部材を変更することで費用は300万円ほど増額するが、メンテナンス費用が30年で1,400万円ほど縮減できるため採用することとした。 |
(意見) |
技術は日々進歩している。今後も、情報収集に努め事業を推進していただきたい。 |
| 議案以外の主な論議 | |
(質問) |
県産品の販路拡大について、販売額が16億8,500万円、対前年比で123パーセントとなったとのことだが、品目はどのようなもので、それぞれの販売額はどれくらいか。また、これからの見込みとして、何が伸びる可能性があると受け止めているか。 |
(答弁) |
戦略品目を10種類選定している。プロデュース事業による平成20年度の販売額で、長崎さちのか、4億1,643万円、長崎アスパラ、4億2,793万円、長崎和牛、3億8,834万円、ごんあじ、8,347万円、長崎たちうお、4,202万円などである。今年度はさらに、対前年度比10パーセントの増を目標としているが、特に期待をしているものは、長崎さちのか、長崎和牛、長崎たちうおである。これらのものを含めてさらに各店舗に対して営業を進めていきたい。 |
(質問) |
企業の倒産件数において全国と長崎県との比較をみると、中小企業経営緊急安定化資金により、企業の倒産防止に一定の効果があったことは評価したい。しかし、まだ経済不況は依然として続いている。今年の年末や年度末における緊急資金のため制度を復活することはないのか。 |
(答弁) |
制度は本年の3月末で一旦終了しているが、これに変わる措置として主な市町に対して依頼をし、例えば長崎市では、県と同様な条件で82億円の資金が創設されている。そのような市町の資金や、政府系金融機関で実施しているセーフティネット貸付の利用状況を勘案しながら県でも制度の復活に向けて準備をしたい。年末、年度末の緊急資金ということを考えると9月議会で計上できるよう検討していきたい。 |
(質問) |
実施時期について、12月からではなく、11月から実施することはできないのか。 |
(答弁) |
実施時期については、年末資金が必要となる時期に合うよう、適切な時期を決定していきたい。 |
(質問) |
390億円の資金のうち、県は金融機関に対し、220億円を無利子で預託をし、金融機関は自己資金、170億円を加えて、1.8パーセントの利率で貸し付けている。金融機関の利回りでいえば3.9パーセントになるとのことだが、金融機関にとっては、リスクのない貸付である。現在の利率1.8パーセントを下げられないのか。 |
(答弁) |
資金規模等は、県としての財政的な力を踏まえ、金融機関とも協調して制度設計した。制度実施の途中で、金融機関利回りを下げた経緯もある。協調融資であることから、金融機関とも協議を行う必要がある。 |
(質問) |
第十一大栄丸転覆沈没事故の船体の引き揚げについて、民間の技術を使いコストをかければ可能かもしれないのであれば、その費用を県が調査してみる考えはないのか。金額は概算であるかもしれないが、その金額を出発点として国に要望することなどができるのではないか。誰が主体性をもって引き揚げについて取り組んでいくと考えているのか。 |
(答弁) |
国は、引き挙げ等についての知見をもっている。県には残念ながらその知見がないので、国にお願いするのが適切と考えている。 |
(要望) |
県は国に対し、要望を行っている以上、成果を出す努力をしていただきたいし、またその結果については、県民に対し説明責任が果たせるよう国・県共にその使命をもって取り組んでいただきたい。 |
(質問) |
エチゼンクラが捕獲された、対馬市尾崎地区は、養殖マグロの基地である。クラゲによる被害が、マグロ養殖に及ぶことはないか。また、クラゲの発生に対しては、どのような対策があるのか。 |
(答弁) |
対策としては、駆除するしか方法がない。具体的な駆除はどうするのか、また、その経費についてどうするのかなどが課題となってくるが、早急に地元の各漁協と打合せをしたい。 また、マグロ養殖への影響であるが、対馬に着く頃の、クラゲの大きさは30センチメートルから40センチメートルと予想される。養殖用の網目はそれよりも小さいので中に入る被害は発生しないと考えている。 |
(質問) |
常時マイナス1メートルを確保するよう排水していれば、今回のような諌早湾干拓地の背後農地の湛水は起きなかったのではないか。 |
(答弁) |
小潮であることは分かっていたため、制限水位のマイナス1.19メートルまで下げていた。その後水位が上がったが、漁業への影響を考慮し南部排水門のみからの排水で可能と判断し対応したが、背後地の水が予想以上に多く排水できず湛水してしまった。 |
(質問) |
今後も、この程度の降雨は予想される。背後地の排水対策も必要なのではないか。 |
(答弁) |
背後地の対策については、平成22年度に排水対策特別事業として、ポンプ機場2箇所と樋門の改修などを考えている。今後は、水位の管理について早めの対応を行い、また、その状況について、農業者、漁業者の皆さんと十分情報交換を行っていきたい。その中で防災という第一義の目的も担保していくよう取り組んでいきたい。 |
(質問) |
管理事務所への侵入があったとの報道があったが、セキュリティの問題としてどのように考えるか。 |
(答弁) |
防災機能の中枢である操作室に外部の方が侵入するということは、背後地の住民の生命、財産に対する危険を引き起こしかねない大きな問題であると受け止めている。危機管理の面から、しっかりとした対策を講じたい。 |
| その他、交わされた論議 | |
|
|