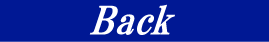意見書・決議
第163号議案「職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例」
及びこれに関連する補正予算案に関する付帯決議
|
上記議案については、若年者への配慮や子育て家庭の支援等、一定理解できる内容が盛り込まれているものの、県内の経済・雇用情勢は依然厳しく、また、平成24年度には財源調整のための基金が枯渇する恐れがあるなど、本県の財政状況も大変厳しい状態にある中、現在ラスパイレス指数が101.5と九州トップにある職員給与をさらに増額することは、県民感情からも容易に納得できるものではない。 記
以上、決議する。 平成19年12月19日 |
長 崎 県 議 会 |
(提出先) 長崎県知事 長崎県教育委員会委員長 長崎県警察本部長 |
金子 古賀 櫻井 |
原二郎 良一 修一 |
様 様 様 |
道路整備の安定的な財源確保を求める意見書
|
社会・経済活動の活性化や産業の振興を図り、地方の自立的かつ一体的な発展をめざすには、各地域の交流促進や連携強化等を支援するネットワークや、豊かな自然と特有の歴史等を活かした観光を支援する周遊ネットワークなど、信頼性が高く定時性を確保できる「規格の高い道路ネットワーク」や、安全かつ安心な生活を支える生活幹線道路が不可欠である。 記
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 平成19年12月19日 |
長 崎 県 議 会 |
(提出先) 内閣総理大臣 総務大臣 財務大臣 国土交通大臣 内閣官房長官 経済財政政策担当大臣 衆議院議長 参議院議長 |
福田 増田 額賀 冬柴 町村 大田 河野 江田 |
康夫 寛也 福志郎 鐵三 信孝 弘子 洋平 五月 |
様 様 様 様 様 様 様 様 |
銃器及び火薬類の取扱いに関する規制強化を求める意見書
|
暴力団関係者による銃器を使用した凶悪事件が相次いで発生している中にあって、今般、佐世保市において、一般市民が散弾銃を使用して多数の人々を殺傷するという、衝撃的な事件が発生した。 記
猟銃等銃器の所持に対する許可及び更新基準や銃弾の保管等の取締の厳格化並びに猟銃等銃器と銃弾の同一人所有を制限するなど、銃刀法をはじめとする関係法令を見直し、効果的な管理手法・制度を構築すること。 以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 平成19年12月19日 |
長 崎 県 議 会 |
(提出先) 内閣総理大臣 経済産業大臣 内閣官房長官 内閣府特命担当大臣 国家公安委員会委員長 警察庁長官 衆議院議長 参議院議長 |
福田 甘利 町村 岸田 泉 吉村 河野 江田 |
康夫 明 信孝 文雄 信也 博人 洋平 五月 |
様 様 様 様 様 様 様 様 |
原油価格の高騰に伴う緊急対策の強化・充実を求める意見書
|
不安定な中東情勢、中国やインド等の経済発展に伴う需要拡大、投機的な先物投資などを要因として原油価格が高騰している。ガソリンをはじめとする各種石油製品の値上げにより空前の高値が続いており、先の見えない価格の高騰は、農林水産業、運輸業、窯業、中小企業等の経営を大きく圧迫するとともに国民生活全般にわたって深刻な影響を及ぼしている。 記
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 平成19年12月19日 |
長 崎 県 議 会 |
(提出先) 内閣総理大臣 総務大臣 財務大臣 農林水産大臣 経済産業大臣 国土交通大臣 内閣官房長官 経済財政政策担当大臣 衆議院議長 参議院議長 |
福田 増田 額賀 若林 甘利 冬柴 町村 大田 河野 江田 |
康夫 寛也 福志郎 正俊 明 鐵三 信孝 大田 洋平 五月 |
様 様 様 様 様 様 様 様 様 様 |
地方議会議員の位置付けの明確化に関する意見書
|
地方議会議員の活動は、単に本会議などの会議に出席し、議案の審議などを行うだけではなく、当該地方公共団体の事務に関し調査研究するための活動や、住民代表として住民意思を把握するための活動などいわゆる議員活動があり、とりわけ都道府県議会議員は、活動区域が広域であることや審議事項が広範多岐にわたることから、その職務は、常勤化、専業化している。
以上、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。 平成19年12月19日 |
長 崎 県 議 会 |
(提出先) 内閣総理大臣 総務大臣 内閣官房長官 衆議院議長 参議院議長 |
福田 増田 町村 河野 江田 |
康夫 寛也 町村 洋平 五月 |
様 様 様 様 様 |