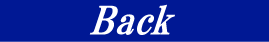意見書・決議
地方財政の充実・強化について
|
地方分権一括法の施行以降、地方自治体の自己決定と自己責任の範囲は大幅に拡大し、地域生活に密着した事務を総合的に担う役割は高まっている。国が法令に基づく事業実施を自治体に義務付け、自治体間の財政力格差が大きい現状においては、地方交付税制度の財源保障機能と財源調整機能を維持し、自治体の安定的な財政運営に必要な一般財源の総額を確保することが重要である。 しかしながら、財政制度等審議会の建議においては、地方交付税を特例的に減額し、国債残高の圧縮に用いることなど、地方自治と公共サービスの基盤を揺るがしかねない状況となっている。 2007年度予算については、「経済財政運営と構造改革に関する基本方針2006」(骨太の方針2006)を基に予算編成作業が進められている。政府が進める効率性やコスト削減という観点だけではなく、地域住民が安心して暮らすのに欠かせない事業の確保や公共サービスの持つセーフティネット機能が担保され、地方への負担の押し付けを行うことのないよう、国に対して、地方財政の充実・強化をめざす立場から、次のことを強く要望するものである。 |
| 記 |
1 |
国が法令に基づく事業実施を自治体に義務づけ、自治体間の財政力格差が大きい現状においては地方交付税制度の財源保障と財源調整の機能を堅持し、自治体の安定的な財政運営に必要な一般財源の総額を確保すること。 |
2 |
地方財政再建と地方財政自立にむけ、国から地方への過剰な関与を見直し、さらなる税源移譲と国庫補助負担金改革を進め、地方自治の確立と分権改革の基盤整備につながる税財政制度の改革を進めること。 |
特定疾患治療研究事業の対象範囲見直しについて
国の難病対策として実施されている特定疾患治療研究事業は、患者の医療費の負担軽減を図るとともに、病態の把握や治療法の研究に大きな役割を果たしており、難病患者や家族の支えとなっている。 しかしながら、厚生労働省の特定疾患対策懇談会において、医療費の公費負担の対象となる特定疾患のうち、パーキンソン病と潰瘍性大腸炎については、患者数が5万人を超え、希少性の条件を溝たさなくなったことを理由として、国では特定疾患治療研究事業の対象範囲を重症患者に絞り込む方向で見直しが検討されている。 この方向での見直しは、除外された患者の医療費の自己負担が増加するとともに、そのことが受診の抑制を招き、病状が悪化することが懸念される。 よって、国に対して、患者が適切な医療を受け、患者及び家族が安心して日常生活ができるよう、パーキンソン病と潰瘍性大腸炎にかかる特定疾患治療研究事業の対象範囲の見直しを行わないよう、強く要望するものである。 |
カネミ油症の仮払金返還等について
カネミ油症については、その被害規模の大きさ、症状の深刻さ、治療法解明の困難さから、多くの被害者が、事件発生から38年という長きにわたり、様々な全身疾患にさいなまれ苦しんできており、将来においても健康の回復は今もって見えていない状況にある。 また、被害者は、国を相手とした損害賠償請求の訴訟で、一旦手にした仮払金について、裁判を取り下げたことにより返還の義務が生じたが、苦しい生活を送る中、経済的にも精神的にも追いつめられ、心の安まることのない日々を送っている者も多い。 現在、仮払金返還債権の免除に関する法案について検討されているところであるが、結論が出るまでには至っておらず、これでは今まで必死に実情を訴え、一日も早いその解決を待ち望んできたカネミ油症被害者は、救われがたい状況に身を置かれたままである。 よって、国に対して、直ちに、被害者の要望にも十分配慮した救済法を成立させるとともに、医療・保健対策の充実等についても引き続き取り組まれるよう、下記のとおり強く要望するものである。 |
記 |
1 |
仮払金返還について |
|
(1) |
仮払金返還の履行延期期間が10年に至っていない債務者についても、債権免除の対象とすること。 |
(2) |
無資力の要件に該当しない債務者についても、最大限の要件緩和を行うこと。 |
|
(3) |
仮払金返還の債務者は仮払金を受領した被害者のみとし、相続人には債権は引き継がれないものとすること。 また、既に債務が相続されている場合は、今後相続人への返還請求を行わないものとすること。 |
|
(4) |
既に仮払金を返還した被害者に対しても、公平な立場から十分な配慮を行うものとすること。 |
2 |
公害病に係る被害者救済並みの取り扱いによる、認定患者の医療・保健対策の充実を図ること。 |
3 |
カネミ油症の人体に及ぼす健康被害について、引き続き調査研究を推進するとともに、治療法の早期確立を図ること。 |
日豪経済連携協定交渉について
我が国と豪州との経済連携協定(EPA)については、日豪政府間で行われていた「日豪経済関係強化に関する共同研究」の報告書が12月4日に取りまとめられ、今後、締結に向けた交渉が開始される見込みである。 我が国の豪州からの輸入状況を見ると、農林水産物の占める割合が高く、しかも我が国にとって極めて重要な米、麦、牛肉、乳製品、砂糖などの品目が含まれている。仮に関税が撤廃され豪州からの輸入が増加した場合、国内農業への直接的な影響だけでも約8000億円にものぼるという試算が公表されており、同様の前提で本県農業への影響を試算すると、約130億円にもなる。 このように、今後の交渉の帰趨如何によっては、日本農業に壊滅的な打撃を与えるばかりか、食料自給率の大幅な低下及び我が国農業・農村の有している多面的機能の喪失につながる恐れがある。特に、米、肉用牛などを主要産物とする当県にとっては、農業者はもとより、県経済全体が大きな打撃を受ける可能性がある。 また、これまで我が国は、WTO農業交渉において、「農業の多面的機能の発揮」と「多様な農業の共存」等の観点から市場アクセスに関する柔軟な取扱いを主張してきている。豪州とのEPAにおいて、WTO交渉における従来の主張から譲歩すれば、これまでの交渉の努力が水泡に帰すこととなるとともに、米国やカナダを含むその他の国々からも同様の措置を求められることにつながりかねない。 よって、政府に対して、日豪EPAの交渉に際し、以下の事項が確保されるよう強く要望するものである。 |
記 |
1 |
米、麦、牛肉、乳製品、砂糖などの重要品目については、除外の対象とするなどの例外措置を確保すること。また、豪州側が我が国の重要品目について十分配慮しない場合は、交渉の継続について中断も含め厳しい判断を行うこと。 |
2 |
WTO交渉における我が国の主張に基づいた整合性のある対応が確保されるよう主張すること。 |
3 |
肉用牛など離島・中山間農業に重要な地位を占めている品目への影響が生じた場合、地域農業のみならず関連産業及び地域経済に及ぼす影響も甚大であることを十分配慮して対応すること。 |
違法な物品調達にかかる再発防止策について
このたび、長崎県が調達する物品に関し、違法な経理処理を行ってきたことが判明した。 このことは、県民の信頼によって支えられている県政を、県職員自ら失墜させた行為であり、決して許されるものではない。 知事をはじめ管理監督責任の地位にある職員等は、議会が議決した予算を適正に執行することを義務づけられているにもかかわらず、これを多年にわたり遵守してこなかった責任は誠に重大である。 県職員一人ひとりがかかる事態を真摯に重く受け止め、公務員として自らその姿勢を正すとともに深く反省し、県民の不信や疑惑を払拭するよう、信頼回復に全力で取り組まなければならない。 よって、本県議会は、知事に対し次のことを強く要請する。 |
1 |
問題の全容を解明し、速やかに県民に明らかにすること |
2 |
責任の明確化と関係職員の厳正な処分を行うこと |
3 |
問題発生の一因となった予算の使い切り主義の見直し等事務制度の改善を図るとともに、外部の知見を活用する等監査制度の改善を図ること |
4 |
すべての県職員の意識改革を図り、法令遵守に徹すること |
5 |
徹底した情報公開を進めること |