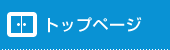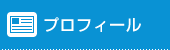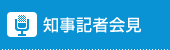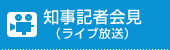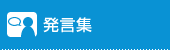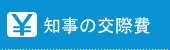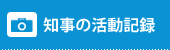長崎県ホームページ
パンくずリスト(現在位置の表示)
知事のページ - 長崎県知事 大石賢吾
令和7年9月4日 令和7年9月定例県議会における知事説明
本日、ここに、令和7年9月定例県議会を招集いたしましたところ、議員の皆様には、ご健勝にてご出席を賜り、厚く御礼を申し上げます。
説明に入ります前に、去る8月6日以降の停滞した前線の影響により、九州各県をはじめ、全国的に記録的な大雨となり、河川の氾濫や土砂災害による甚大な被害が発生しております。 お亡くなりになられた方々並びにご遺族の皆様に心から哀悼の意を表しますとともに、負傷され、また被害を受けられた方々に衷心よりお見舞いを申し上げます。 本県においては、幸いにして人的被害は生じておりませんが、線状降水帯が発生し、各地域で住家や道路の損壊等の被害が発生したところであり、国による激甚災害への指定状況を注視するとともに、被害状況を確認し、迅速に必要な対策を講じてまいります。
また、先の参議院議員選挙においてご当選されました古賀友一郎議員に対しまして、心からお慶びを申し上げますとともに、今後とも、国政の場において一層のご活躍をいただき、本県の発展のためにお力添えを賜りますよう、お願い申し上げます。
それでは、開会に当たり、当面する諸課題について所信を申し述べますとともに、前定例会以降、今日までの県政の重要事項について、ご報告を申し上げたいと存じます。
新たな総合計画の策定
新たな総合計画については、去る6月定例会において、「こども」「くらし」「しごと創造」「にぎわい」「まち」の5つの柱のもと、12の基本戦略と、その戦略に基づく施策を掲げた素案骨子をお示しし、ご議論いただいたところであります。 県では、素案骨子に対する県議会や有識者による懇話会でのご議論のほか、県内各地域での意見交換会や市町のご意見等を踏まえながら、内容の検討を深め、今般、計画素案を策定いたしました。 計画素案では、「ながさきの誇りと希望を力に、みんなで夢あふれる未来をひらく」を基本理念とし、県民一人ひとりの長崎県に対する誇りや将来への希望を原動力として、新たな時代を切り拓き、「新しい長崎県づくり」に挑む姿勢を示しております。 この基本理念のもと、地域社会の基盤となる経済の活性化に向けた力強い産業の実現や稼ぐ意識・力の底上げに加え、本県の将来を担うこどもたちの能力と可能性を高めるとともに、すべての世代の方々が健康で安全・安心に暮らせる社会環境づくりなどに、これまで以上に力を注ぐこととしております。 また、今後の社会経済情勢等を見据えた新たな展開に向けて、各産業分野の活性化による県民所得の向上をはじめ、地方創生や離島振興、国際県といったテーマ別の重点的な取組を掲げるとともに、地域別の取組では、県内各地域の特性を活かした施策等を織り込むなど、県勢の更なる発展を目指してまいりたいと考えております。 さらに、施策の構築にあたっては、国の地方創生2.0の考え方等も踏まえつつ、本県特有の課題についてもきめ細かな対応を図るとともに、デジタル技術の活用や戦略的情報発信・ブランディングの展開、「稼ぐ」視点の反映等の基本的な姿勢を持ち、分野横断的な取組を充実・強化したところであります。 今後、県議会でのご議論やパブリックコメント等による県民の皆様のご意見をお伺いしながら、さらに検討を重ね、今年度中の計画策定を目指し、取り組んでまいります。
ながさきブランディング・情報発信戦略の策定
本県が、国内外の多方面から選ばれる「新しい長崎県」を目指していくためには、自然・歴史・文化・環境など本県の多彩な魅力やそのポテンシャルを活かし、本県の総体的なイメージ向上につながる「ながさきブランド」の構築が必要であると考えております。 そのため、関係団体や行政機関及び観光、食、地域振興などの分野における有識者や若い方々の意見を取り入れながら、ブランディング及び情報発信の戦略を策定いたしました。 その中で、長崎県民の包容力や多様性とともに、県民一人ひとりの魅力が咲き、希望が輝くことをイメージしたシンボルマークとブランドメッセージ「みなが咲き、ながさき。」を作成したところであります。 戦略においては、このブランドメッセージ等を活用しながら、まずは、県民の皆様に長崎県の魅力を再認識していただくためのインナーブランディングに取り組みつつ、県外の方にも魅力を発信するアウターブランディングにも併せて取り組むことで、県民の皆様がふるさとに誇りを持ち、将来に希望を抱ける長崎県の実現を目指していくこととしております。 今後は、長崎県のブランドの考え方を県民の皆様にしっかりとお伝えし、市町や民間、関係団体の皆様と一体となってブランディングの取組を進めてまいります。
九州新幹線西九州ルートの整備促進
今月23日に開業3周年を迎える西九州新幹線については、令和6年度の1日あたりの利用者が7千人を超え、開業当時の水準を継続して上回るなど、順調に推移しているものと認識しております。 こうした一方、未整備区間である新鳥栖〜武雄温泉間については、国土交通省と佐賀県による幅広い協議が行われておりますが、未だ整備方式が決まっておらず、議論が進展するためには、西九州新幹線の効果を拡大させながら、全線フル規格による整備に向けた一層の気運醸成が重要であると考えております。 そのような中、去る8月19日、佐賀県の山口知事、JR九州の古宮社長との三者で、九州新幹線西九州ルートの現状や課題について意見交換を行いました。 私からは、議論を進めるため、根拠のあるデータで具体的に検証する必要性を示し、環境影響評価の実施等を国に求めることを提案いたしました。 今回の意見交換においては、フリーゲージトレイン導入断念の経緯を踏まえ、国に具体的な解決策を求めること及び間を置かずに次回の意見交換を実施することについて、三者間で認識が一致したことは、意義あるものと受け止めております。 さらに、石破内閣総理大臣が7月に本県を訪れた際に、九州新幹線西九州ルートに言及されたことを受け、去る9月4日には、県選出国会議員の皆様や外間県議会議長、沿線市長、市議会議長、県内経済団体の皆様とともに、首相官邸を訪問し、林内閣官房長官同席のもと、石破総理に対し、フリーゲージトレイン導入断念に伴い増加が見込まれる地方負担など、想定される課題に対する具体的な解決策の提示や環境影響評価の早期実施を強く要望してまいりました。 石破総理は、引き続き、地元に丁寧に説明し、佐賀県の理解を得るよう努力すると答えられ、本県の思いや地元の熱意をしっかりと受け止めていただいたものと考えております。 また、同日、国土交通省に対し、国を交えた関係者間での協議の実施を求めるとともに、自由民主党の森山幹事長に対し、与党PT九州新幹線(西九州ルート)検討委員会の早期開催を要請いたしました。 去る8月29日には、福岡市において、県内経済団体の主催によるシンポジウムが開催され、九州各地から経済団体や行政関係者など、約800名の方々が参加されました。 このシンポジウムでは、新幹線研究の第一人者である中川大(なかがわだい)京都大学名誉教授から、世界と日本における高速鉄道の現状について講演があったほか、パネルディスカッションにおいては、関西直通運行でのインバウンドの拡大や全線フル規格による地域の経済発展が議論されるなど、西九州地域が全国の新幹線ネットワークに繋がる必要性について、理解が深まったものと考えております。 県としては、引き続き、市町や関係団体と連携しながら、新幹線効果の拡大に取り組むとともに、政府・与党をはじめ関係者に対して、議論の進展や課題の解決について働きかけるなど、西九州地域全体の発展に資する全線フル規格での整備を目指し、力を注いでまいります。
ミカンコミバエの発生拡大
みかんやびわなどの果実等に寄生する重要病害虫であるミカンコミバエが、本県において、6月中旬以降、過去最大であった令和3年度を大きく上回るペースで捕獲、確認されております。 そのため、県では、国の植物防疫所や市町、JA等の関係機関と一体となり、直ちに捕獲のための誘殺板の設置などによる初期防除を実施いたしました。 また、捕獲数が増加した8月には、緊急対策会議を開催のうえ、防除範囲を拡大するとともに、地域の生産者や住民の皆様にご協力いただき、成熟した果実等の除去を行うなど、対策の強化を図っております。 さらに、今月からは、人による散布が困難な山間部等への航空ヘリによる誘殺板の緊急散布を実施する予定としているところであります。 仮に、これ以上捕獲地域が拡大した場合は、本県の主要な品目である、みかんなどの出荷への影響も懸念されるため、県としては、産地への影響が生じないよう、危機感をもって、引き続き、国や市町、JA等の関係機関と緊密に連携しながら、防除対策の実施に万全を期してまいります。
最低賃金に関する答申
去る9月2日、長崎地方最低賃金審議会から長崎労働局長に対して、本県の最低賃金を現行の953円から78円引き上げ、1,031円とするよう答申がなされました。 物価の上昇が続く中、県民の生活を守るためには、賃上げによって消費を喚起し、経済の好循環を図っていくことが重要であると認識しておりますが、一方で、急激な最低賃金の引上げによって、県内中小企業・小規模事業者の経営環境は厳しくなるものと想定されます。 今後とも、県では、国の動向を注視しながら、賃上げに必要な原資が確保され、構造的な賃上げが実現するよう、企業の生産性向上の支援や商工会・商工会議所の経営指導員による伴走型支援の強化など、中小企業・小規模事業者の経営発展に向け、支援の強化を図ってまいります。
前畑弾薬庫の移転・返還にかかる日米合意
去る8月28日、防衛省から、佐世保弾薬補給所(前畑弾薬庫)の移設先の施設の配置案について、日米合同委員会で合意されたとの発表がありました。 また、9月5日には、金子防衛大臣政務官から、合意したことを直接お伝えいただくとともに、移設先の配置案の概要や移設までの今後の見込みについてご説明いただきました。 前畑弾薬庫の移転・返還については、平成23年の日米合同委員会での返還合意から、すでに14年が経過しているものの、移設先の施設配置案が決定されないことから、工事着工にも至らない状況にあり、これまで、県としても、佐世保市と一体となって、配置案を早急に決定し、事業の進捗を図るよう国へ強く要望してまいりました。 今般、日米間で配置案の合意がなされたことは、佐世保市や地域の皆様にとって長年の課題である前畑弾薬庫の移転・返還に向けた重要な一歩であると受け止めており、私自身も機会を捉えて米国関係者に働きかけてきたことから、大変喜ばしく思っております。 これまでの間、多大なるご尽力を賜りました本県選出国会議員や県議会議員の皆様をはじめ、関係の皆様方に対し、心からお礼を申し上げます。 県としては、引き続き、佐世保港のすみ分けの早期実現に向け、佐世保市と連携しながら取り組んでまいります。
原子力発電施設等立地地域の財政支援対象拡大
去る8月29日、国から、原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法の対象地域について、従来、原発から概ね10キロ圏内であったものを、概ね30キロ圏内に拡大することが発表されました。 本県では、佐世保市、平戸市、松浦市、壱岐市の4市が、この拡大する圏内に該当し、今後、対象地域に指定されると、同法によるインフラ整備に対する財政支援の対象となります。 4市においては、平成24年の原子力災害対策特別措置法の改正以降、立地自治体と同等の原子力災害対策を実施する責務を課されているにもかかわらず、立地自治体との財源格差は解消されることなく、不安と負担を強いられてきました。 こうした状況を踏まえ、県では、本年1月には、県内関係4市と、また、6月には、原発周辺自治体6府県とともに、国に対して、格差是正の要望を行ってきたところであり、このたびの決定は、立地自治体との格差是正に向けた大きな前進であると受け止めております。 これまでの間、多大なるご尽力を賜りました本県選出国会議員や県議会議員の皆様をはじめ、関係の皆様方に対し、心からお礼を申し上げます。 今後、国は、さらなる支援措置を検討するとしていることから、県としては、国の動向を注視しつつ、県民の安全・安心の確保に向けて、引き続き、関係自治体と連携して取り組んでまいります。
国境離島地域の振興
本県は、特定有人国境離島地域に全国最多の40島を有しており、平成29年の有人国境離島法の施行以来、法に基づく国の交付金を最大限に活用しながら、関係市町や地域の皆様方と一体となって、雇用機会の拡充をはじめ、航路・航空路の運賃低廉化、輸送コストの支援、滞在型観光の促進など、地域社会の維持・振興に全力で取り組んでまいりました。 こうした結果、これまでの8年間で、1,600人を超える新たな雇用の場が創出され、一部の地域では、人口の社会増が達成されるなど、地域の活力向上や雇用の確保、交流人口の拡大等において成果が現れているものと考えております。 一方で、進学や就職に伴う若者の転出、自然減の拡大に伴う人口減少が本土地域以上に進んでおり、有人国境離島地域が果たす国家的意義も鑑みると、当該地域の保全や地域社会の維持・振興の重要性は一層増していると考えられることから、令和9年3月末に期限を迎える現行の有人国境離島法の改正・延長が必要不可欠であると認識しております。 そのため、去る8月22日、外間県議会議長や関係市町の皆様とともに、坂井内閣府特命担当大臣をはじめ関係者に対して、改正・延長に向けた要望活動を行ったところであります。 今後、県では、関係市町や県議会からの制度改正の要望等をしっかりとお聞きしながら、意見書のとりまとめを丁寧に進めるとともに、私が先頭に立って関係皆様方と一丸となった要望活動を実施するなど、支援策の充実・強化を伴う所要の法改正が確実に行われるよう、国に対して強く働きかけてまいります。
被爆体験者の救済と核兵器廃絶に向けた取組
去る8月9日、長崎に原爆が投下されてから、80年を迎えました。 長崎、広島で開催された原爆犠牲者慰霊平和祈念式典には、両県知事が、初めてそれぞれの式典に参列し、犠牲になられた方々のご冥福をお祈りいたしました。 私も被爆県の知事として、核兵器廃絶に向けた決意と平和への誓いを新たにしたところであります。 式典当日には、被爆者団体と石破総理の面会に、被爆体験者の団体も同席されました。 県としても、被爆体験者の皆様の切実な思いを受け止め、長崎市等と連携しながら、被爆体験者の救済に力を尽くしてまいります。 また、昨年、日本原水爆被害者団体協議会がノーベル平和賞を受賞し、今年7月にはノルウェー・ノーベル委員会のフリードネス委員長が本県を訪れ、核兵器の非人道性を訴えられるなど、核兵器廃絶に向けた機運は高まりを見せています。 このような中、核兵器を取り巻く国際情勢は、一段と厳しさを増していることから、これまで以上に核兵器の非人道性を訴えることに加え、核抑止が安全保障の唯一の選択肢であるのかという問題提起を行うとともに、全世界の方々に、核の問題を「自分事」として捉えていただくことが極めて重要であると考えております。 この認識のもと、長崎市や広島県、関係団体等と連携し、被爆の実相や核兵器廃絶の必要性について、より一層、力強く世界に訴えてまいります。
長崎〜釜山間の国際航空路線の臨時運航
このたび、本県の友好交流都市である韓国・釜山広域市の金海国際空港と長崎空港を結ぶ臨時便が、エアプサンにより運航されることが決定いたしました。 今回の運航は、韓国からのインバウンド客のみを対象として、10月1日から11日まで、合計8往復、16便が予定されており、多くの方々に本県の魅力をお伝えする機会になるものと期待しているところであります。 県としては、人口300万人を超える韓国有数の経済圏を持ち、同国南部の中心都市である釜山広域市と本県を結ぶ定期便の早期開設や他の国・地域からの国際航空路線誘致に向けた取組を推進するなど、インバウンド需要を取り込み、本県経済を活性化させるため、海外からの交流人口のさらなる増加につなげてまいります。
ながさきピース文化祭2025の開幕
「ながさきピース文化祭2025」については、令和3年7月の開催内定以降、県内全市町をはじめ、文化、福祉、教育、経済など各分野の皆様と連携し、基本構想や実施計画の策定、各種プログラムの検討、機運醸成や参加者の受入環境整備など、様々な準備を進めてきたところでありますが、いよいよ、今月14日に開幕を迎えます。 本文化祭においては、「文化をみんなに」のキャッチフレーズのもと、11月30日までの78日間、県内全域で 180を超える多彩な文化イベントを実施いたします。 その間、県内外からの総参加者数として、約190万人を見込んでおり、県を挙げて、参加される方々をおもてなしの心でお迎えしたいと考えております。 また、本文化祭の開会式については、天皇皇后両陛下のご臨席を賜るとともに、併せて、本県の地方事情御視察には 愛子内親王殿下もご同伴されることとなっております。 両陛下のご来県はご即位後初めてであり、愛子内親王殿下におかれても初めて長崎へお越しになることから、本県にとって、大変光栄なことであり、この上ない喜びであります。 さらに、開会式には、本県ゆかりの著名人にもご出演いただくことから、一般観覧者の募集には、県内外から数多くの応募があるなど、大きな注目を集めており、文化祭の幕開けを飾るに相応しい開会式となるよう、現在、式典スタッフや出演者等関係者が一丸となり最終確認を行っているところであります。 県としては、多くの皆様にとって心に残る文化祭となるよう、引き続き、関係者と連携し、開催に向けた準備及び期間中の大会運営に全力を注いでまいります。
ツール・ド・九州2025佐世保クリテリウムの開催
国際サイクルロードレース「ツール・ド・九州2025」については、10月10日の開催まで残すところ1カ月余りとなりました。 本大会は、佐世保市でのクリテリウムを皮切りに、福岡県、熊本県、宮崎県、大分県においてロードレースが開催され、国内外18チーム、約100名の選手の参加のもと、4日間にわたり熱戦が繰り広げられる予定となっております。 大会には、ツール・ド・フランスなど世界最高クラスのレースに出場経験のある選手も参加されることから、世界トップクラスのスピードと技術を体感することができる大変貴重な機会であり、是非、多くの方々に観戦していただきたいと考えております。 また、大会当日から翌日にかけて、競技の魅力を伝えるトークショーや体験会、物産販売ブースの設置など、様々な関連イベントも開催する予定としており、会場周辺を大いに盛り上げるとともに、本県の多彩な魅力についても、しっかりと発信してまいりたいと考えております。 県としては、佐世保クリテリウムが、佐世保市を中心とする県北地域の振興や交流人口の拡大に繋がるよう、九州経済連合会を中心とした実行委員会や佐世保市、競技団体、観光団体等と連携しながら、開催に向けた最終調整に万全を期してまいります。
大阪・関西万博における出展
本年4月から開催されている「大阪・関西万博」については、本県並びに九州の観光や物産等の魅力を国内外に広く発信し、誘客に繋げる貴重な機会と捉え、今月3日から5日までの3日間、「九州の宝を世界へ―TreasureIsland・KYUSHU―」をテーマに九州7県合同で出展を行ってまいりました。 本県においては、豊富な食や絶景の紹介、伝統工芸の展示や体験、ステージイベントなどを通じて、多くのご来場の皆様に本県の魅力を体感いただいたところであります。 私も、初日のオープニングイベントに出席し、本県の豊かな自然や歴史、文化、食といった多様な魅力を、幅広い層の方々に積極的にPRしてまいりました。 また、万博の開催期間に合わせて、大阪駅に隣接する商業施設において、本県の観光資源や物産等のPR、西九州新幹線の魅力発信などを引き続き実施することとしており、関西エリアをはじめ、国内外における本県の認知度向上を図り、観光誘客や県産品の販売促進につなげてまいります。
石木ダムの推進
石木ダムについては、渇水や洪水などの自然災害から地域の皆様の安全・安心の確保を図るうえで必要不可欠な事業であり、早期完成を目指す必要があることから、工期である令和14年度までの確実な完成に向け、工事工程に沿って着実に工事を進めております。 令和4年の知事就任当時は、主に付替県道工事を進めながら、本体左岸部の本格的な掘削に着手しようとしていたところでありました。 その後、重ねて現地に足を運び、川原地区にお住まいの皆様にお会いしたり、一緒に現地を歩いて見て回ったほか、複数回の話合いを行うなど、対話による解決に向けて、積極的に取り組むとともに、工程に沿って途切れることなく工事を進めてまいりました。 具体的には、付替道路工事の新たな区間やダム本体の本格的な掘削工事への着手、迂回道路工事の進捗などにより、付替県道の工事については、3号橋の橋脚が完成するとともに、迂回道路は今年度の完成が見込まれるなど、着実に進展しております。 去る8月31日には、宮島佐世保市長、波戸川棚町長とともに建設現場の視察を行ったところであります。 これまでの工事区間に加え、ダム本体工事のための工事用道路への着手状況など、着実な進捗を確認し、事業にご協力いただいてきた地権者の皆様への感謝と施工業者をはじめとした関係者の皆様のご尽力を改めて実感いたしました。 一方で、川原地区にお住まいの13世帯の皆様のご理解とご協力を得たうえで事業を進めることが最善との考えに変わりはなく、今年度、川棚町において開催している石木ダムの技術的な疑問等に対する説明会については、8月23日に3回目を開催し、川棚川における治水計画や費用対効果、環境への影響などに関する市民団体からの質問に対し、県の考えを丁寧にご説明させていただいたところであります。 議論が平行線に終わったものもありますが、県としては、引き続き、説明の努力を続けてまいります。 また、佐世保市及び川棚町とともに策定を進めております水源地域整備計画については、昨年12月に素案の公表を行い、広くご意見を伺ったところであります。 今後、地元説明会を開催したうえで、その結果も踏まえ、国へ計画を提出する予定としております。 石木ダムは、安全・安心の確保を図るうえで必要不可欠であり、併せて、ダム周辺地域の環境整備がなされることで、関係住民の皆様の生活の安定と福祉の向上にもつながるものであると考えており、県としては、ダムの一日も早い完成に向けた行政の責務の重さを改めて認識したうえで、引き続き、佐世保市及び川棚町と一体となって、事業の推進に全力を注いでまいります。
強靱な県土づくり
県では、強靱な県土づくりに向けて、これまで、国の「防災・減災、国土強靱化のための5か年加速化対策」予算を最大限活用しながら、防災インフラの整備や交通ネットワークの強化、インフラの老朽化対策などを積極的に推進してまいりました。 こうした中、国の5か年加速化対策は、本年度が対策期間の最終年度となっておりますが、多くの離島・半島を有する本県において、激甚化・頻発化する自然災害から県民の生命・財産・暮らしを守り、支えていく必要性は、ますます高まっており、強靱な県土づくりに向けた取組をしっかりと継続していくことが重要であると考えております。 そのため、去る7月30日、外間県議会議長をはじめ、県選出国会議員、市町、経済界など関係皆様とともに、本年6月に策定された「第1次国土強靱化実施中期計画」に基づく継続的で安定的な予算の確保や資材価格、人件費の高騰等の影響への適切な対応などについて、国土交通省や財務省等に対する要望活動を行ったところであります。 県としては、引き続き、国に対して、本県の実情をしっかりと訴え、強靱な県土づくりに必要な予算の確保に努めてまいります。
企業誘致の推進
去る7月17日、埼玉県に本社を置くコージンバイオ株式会社が、大村市への立地を決定されました。同社は、5年間で42名を雇用し、再生医療や免疫治療の細胞培養に用いる培地の開発や製造などを行うこととされております。 また、8月1日には、東京都に本社を置く郵船出光グリーンソリューションズ株式会社が、長崎市への立地を決定されました。同社は、5年間で25名を雇用し、発電所や工場等で使用されているボイラの燃焼制御について、AIを搭載したシステム開発などを行うこととされております。 今後とも、雇用の拡大と地域経済の活性化を目指して、地元自治体や関係機関と連携しながら、企業誘致の推進に力を注いでまいります。
スポーツの振興
この夏、本県の中・高校生が各種全国大会において、見事な活躍を見せてくれました。 去る7月23日から8月20日まで、中国地方5県を主会場として開催された全国高等学校総合体育大会において、 ソフトボール競技男子で大村工業高校、登山競技女子で長崎北陽台高校、ウエイトリフティング競技女子76kg超級で西彼農業高校の森七菜実(もりなみ)選手がそれぞれ優勝するなど、団体・個人合わせて36の入賞を果たしました。 また、7月25日から8月23日まで東京都を中心に開催された全国高等学校定時制・通信制体育大会においても、卓球競技女子団体で鳴滝高校通信制、バドミントン競技女子団体でこころ咲良高校通信制が優勝を飾りました。 さらに、8月17日から25日まで、本県をはじめ九州各県で開催された全国中学校体育大会においては、団体・個人合わせて9の入賞を果たしました。 一方、成年競技では、8月8日に東京都で行われた彬子女王杯第1回全日本女子銃剣道選手権大会において、里麻衣(さとまい)選手が優勝を飾りました。 選手並びに指導に当たられた関係者の皆様のご健闘を心からたたえるとともに、今後とも、県民に希望と活力を与えるスポーツの振興と競技力の向上に力を注いでまいります。 さらに、9月27日からインドで開催されます「ニューデリー2025世界パラ陸上競技選手権大会」の男子400m知的障害に、本県在住の臼木大悟(うすきだいご)選手が出場されます。 障害者スポーツにおける本県在住選手の活躍は、県民に勇気と感動を与えるものであり、ふるさと長崎の代表として世界の舞台で大いに活躍されるよう期待いたします。
次に、議案関係についてご説明いたします。 まず、補正予算でありますが、今回は、国庫補助事業の内示等に伴う事業費の追加、その他緊急を要する経費について編成いたしました。 一般会計11億6,964万円の増額 補正をしております。 この結果、現計予算と合算した本年度の一般会計の歳入歳出予算額は、7,433億17万6千円 となり、前年同期の予算に比べ、 51億8,567万8千円 の増となっております。 次に、予算以外の議案のうち、主なものについてご説明いたします。 第90号議案「長崎県議会議員及び長崎県知事の選挙における選挙運動用自動車の使用等の公営に関する条例の一部を改正する条例」は、公職選挙法等の一部改正に伴い、所要の改正をしようとするものであります。 第91号議案「県立高等学校等条例の一部を改正する条例」は、県立中学校及び県立高等学校の入学選抜手数料について納付方法を変更することに伴い、所要の改正をしようとするものであります。 第96号議案「契約の締結の一部変更について」は、一般国道383号橋梁補修工事(平戸大橋・橋梁補修工)について、工事内容の一部変更に伴い、契約金額を変更しようとするものであります。 第97号議案「財産の取得について」は、大村臨海工業用地を取得することについて、議会の議決を得ようとするものであります。 第101号議案は、長崎県公安委員会の委員の任命について議会の同意を得ようとするものであります。 委員といたしまして、 糸屋悦子氏 を任命しようとするものであります。 適任と存じますので、ご決定を賜りますよう、よろしくお願いいたします。 なお、公安委員会委員を退任されます、 森拓二郎委員 には、在任中、多大のご尽力をいただきました。この機会に厚くお礼申し上げます。 第102号議案は、長崎県土地利用審査会の委員の任命について議会の同意を得ようとするものであります。 委員といたしまして、 藤森弘行氏 松尾佐和子氏 吉田護氏 石橋知也氏 清心由紀美氏 佐藤義高氏 城前奈美氏 を任命しようとするものであります。 いずれも適任と存じますので、ご決定を賜りますよう、よろしくお願いいたします。 なお、土地利用審査会委員を退任されます、 五島聖子委員 西岡誠治委員 成田真樹子委員 には、在任中、多大のご尽力をいただきました。この機会に厚くお礼申し上げます。 その他の案件については、説明を省略させていただきますので、ご了承を賜りたいと存じます。
以上をもちまして、本日提出いたしました議案の説明を終わります。 なにとぞ、慎重にご審議のうえ、適正なるご決定を賜りますようお願い申し上げます。