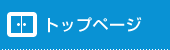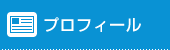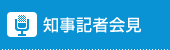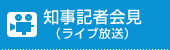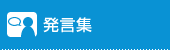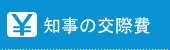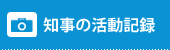長崎県ホームページ
パンくずリスト(現在位置の表示)
知事のページ - 長崎県知事 大石賢吾
令和7年6月9日 令和7年6月定例県議会における知事説明
本日、ここに、令和7年6月定例県議会を招集いたしましたところ、議員の皆様には、ご健勝にてご出席を賜り、厚く御礼を申し上げます。
説明に入ります前に、去る4月6日、壱岐沖で、対馬市から患者を搬送していた民間医療搬送用ヘリコプターの事故により、3名の方々がお亡くなりになられました。 離島の救急医療の要として重要な役割を担ってきたヘリコプターの事故で、尊い命が失われたことは、痛恨の極みであります。 県民を代表して、お亡くなりになられた方々に心から哀悼の意を表しますとともに、ご遺族並びに関係者の皆様に衷心よりお悔やみ申し上げます。 多くの離島や半島を有する本県において、ヘリコプターによる患者搬送は、救命率の向上や後遺症の軽減を図るなど、命を守るために欠かせないものであります。 その中核を担う県ドクターヘリは、事故を起こしたヘリと同型であったため、国土交通省からの指示に基づく検査等を行い、5月30日から運航を再開しております。 県ドクターヘリの運航休止期間中、救急患者の搬送にご対応いただいた佐賀県や海上自衛隊等の関係皆様方に心からお礼を申し上げます。 県としては、引き続き、ヘリコプターの安全運航を徹底し、救急医療体制に支障がないように努め、県民の安全安心の確保を図ってまいります。 また、去る、4月21日にご逝去されました前ローマ教皇フランシスコ台下に謹んで哀悼の意を表します。 前ローマ教皇フランシスコ台下におかれましては、本県における潜伏キリシタンの歴史や被爆の経験に心を寄せていただきました。 特に、令和2年11月に本県をご訪問になられた際には、原爆落下中心地においてメッセージを発信されるなど、かねてより、県民の悲願である核兵器廃絶を世界に向けて訴えてくださいました。 そのご功績に改めて深謝いたしますとともに、安らかなるご永眠を心からお祈り申し上げます。 第267代ローマ教皇に選出されましたレオ14世台下におかれましても、世界に向け、引き続き平和のメッセージを発信いただくとともに、被爆地長崎をご訪問され被爆の実相に触れていただきたいと考えております。 次に、このたび、県議会議員にご当選されました田川正毅議員に対しまして、心からお慶びを申し上げます。 それでは、開会に当たり、当面する諸課題について所信を申し述べますとともに、前定例会以降、今日までの県政の重要事項について、ご報告を申し上げたいと存じます。
社会経済情勢とその対応
本県の景気は、生産活動の増加や所得環境の改善などから、「緩やかに回復している」とされておりますが、エネルギー・食料品価格等の物価高騰が依然として続いており、昨今の米国の関税措置などにより、県民生活や経済活動へのさらなる影響が懸念されるところであります。 県では、これまで、プレミアム付き商品券などの生活支援や、生産性向上のための設備等の導入支援をはじめ、国や市町等と連携しながら、物価高騰対策を講じてきております。 また、米国関税措置の影響を受ける県内中小企業の資金繰りに万全を期すため、県の制度融資である「緊急資金繰り支援資金」の取扱いを7月1日から開始することとしており、引き続き、社会経済情勢の動向を注視し、必要な対応を図ってまいります。
新たな総合計画の策定
近年、人口減少や少子・高齢化等に伴う人口構造の変化に加え、デジタル技術の進展やエネルギー・物価の高騰、気候変動の影響などにより、本県を取り巻く社会経済情勢や人々の意識にも大きな変化が生じているものと認識しております。 県では、こうした潮流を的確に捉えながら、本県の将来像を見据え、ポテンシャルや特性を最大限に活かし、グローバル社会における競争力を高め、県勢の持続的な発展に繋げていくために、令和8年度以降の5年間の政策の方向性を示す新たな総合計画について、今般、素案骨子を策定したところであります。 素案骨子においては、基本理念の考え方として、国の地方創生2.0の基本姿勢と同様に、当面、人口や生産年齢人口が減少するという事態を正面から受け止めたうえで、都市と地方や地方同士の人材交流・人材循環を促進しながら、人口減少社会の中においても経済成長を図り、活力ある地域社会づくりに取り組み、将来にわたり持続的な発展を目指してまいりたいと考えております。 そのため、多様な主体と連携し、地域の力を結集しながら、地域社会の基盤となる経済の活性化に向けた力強い産業の実現とともに、若者や女性をはじめ誰もが活躍・チャレンジできる環境づくり、最先端技術の効果的な活用による稼ぐ意識・力の底上げなどに力を注ぐこととしております。 また、本県の優位性を活かし、国内外との多様な交流を促進することに加え、本県の将来を担うこどもたちの能力と可能性を高めることを社会全体で支えるほか、多様性が尊重され、全世代の方々が健康で安全・安心に暮らせる社会環境づくりなどにも積極的に取り組んでまいります。 こうしたことから、次期計画については、実効性の高いものとなるよう、「こども」「くらし」「しごと創造」「にぎわい」「まち」の5つの柱のもと、12の基本戦略と、その戦略に基づく施策を掲げるとともに、本県及び県内各地域の特性等を踏まえた分野別並びに地域別の取組を盛り込むことについても、検討しているところであります。 併せて、厳しい財政状況の中においては、施策の推進にあたり、新たな財源確保対策を含め、さらなる税財源の充実・強化に努めてまいりたいと考えております。 また、概ね10年後のありたい姿として先行的に策定した「新しい長崎県づくりのビジョン」とタイアップするとともに、地方創生2.0をはじめ国の政策と連動するほか、総合計画と同様に令和7年度末で終期を迎える「第2期長崎県まち・ひと・しごと創生総合戦略」とも整合を図りながら、一体的に検討を進めてまいりたいと考えております。 今後、県議会のご意見を十分にお聴きしながら検討を重ね、県民の皆様のご意見も踏まえつつ、今年度中の計画策定を目指してまいります。
防災対策
去る4月7日に五島市で発生した林野火災については、幸いにして、人的被害や住宅等の被害が発生することなく、翌8日に鎮圧され、10日に鎮火が確認されました。 火災発生以降、地元消防による地上からの消火活動に加え、県においても、五島市からの要請を受け、県防災ヘリコプターを出動させるとともに、陸上自衛隊に対して災害派遣要請を行い、連携して空中からの消火活動を実施いたしました。 また、県においては、長崎県広域消防相互応援協定に基づき、長崎市、佐世保市、県央地域広域市町村圏組合、新上五島町の各消防にも、協定締結後初めての広域応援要請を行い、地上からの消火活動にあたっていただきました。 私も、現地の被害状況を確認してまいりましたが、連携した消火活動等により、被害が最小限に食い止められたと実感したところであり、ご尽力いただいた全ての関係機関の皆様に心から感謝を申し上げます。 県としては、市町や関係機関と連携して、火災予防の周知啓発に努めるとともに、今回の経験を活かしつつ、さらなる訓練等を通じて、より迅速かつ的確な消火活動に繋げてまいります。 去る3月31日、南海トラフ地震の被害について、国は、最新の知見や防災対策の進捗等を踏まえ、30センチメートル以上の浸水地域と避難者数が全国で3割増加するなどといった新たな想定を公表しました。 本県の被害想定についても、死者数が最大で80人であったものが500人に、要救助者数が400人から1,100人になるなど、見直し前と比較して、大幅に増加しております。 今回の見直しに伴い、国から、大津波などによる被害が想定される地域を含む都府県に対し、南海トラフ特措法に基づく「南海トラフ地震防災対策推進地域」の指定に関する意見照会があり、本県は、指定基準を満たす7市にも意向を確認のうえ、先月、指定に異議がない旨を回答いたしました。 併せて、広域防災体制の一体性を確保する必要があるため、津波高が指定基準よりわずかに低い新上五島町についても、町の意向を踏まえ、指定を求める意見を提出したところであります。 今後、国による地域指定が行われる予定であり、それを受け、県においては、「南海トラフ地震防災対策推進計画」を策定し、県民の安全・安心の確保に力を注いでまいります。
半島地域の振興
本年3月末が期限となっていた半島振興法については、去る3月26日に改正法が成立し、令和17年3月までその期間が延長されたところであります。 この間、ご尽力を賜りました本県選出国会議員の皆様をはじめ県議会及び関係皆様方に、心から感謝申し上げます。 今回の改正では、本県として、能登半島地震を踏まえ、特に強く要望してまいりました「半島防災」が目的や基本理念に明記されるとともに、配慮規定に「道路等の交通施設、水道、下水道等の施設の整備」、「災害応急対策・復旧に係る体制整備」などの項目が新たに盛り込まれたところであります。 県としては、国の基本方針に基づき、地域の特性に応じた実効性のある半島振興計画を速やかに策定するとともに、関係市町等と連携しながら、半島地域の自立的発展に向けて取り組んでまいります。
長崎空港の発展に向けた取組
長崎空港は、昭和50年に、大村湾に浮かぶ箕島を埋め立てた世界初の本格的海上空港として誕生以来、長崎の空の玄関口として本県の発展に大きな役割を担ってまいりました。 昨年度の利用者数は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大による利用者の落ち込みを乗り越え、5年ぶりの300万人台となる約307万人を記録しており、平成30年度に記録した過去最高利用者数の約94%まで回復しております。 こうした中、去る5月1日、多くの関係者のご出席のもと、開港50周年の記念セレモニーが開催されたところであり、改めて、これまで長崎空港の開港・発展にご尽力いただいた関係者の皆様に心からお礼を申し上げます。 県では、現在運航されている国内9路線と国際2路線の11の定期路線の利用促進に加え、新たな航空路線の誘致に積極的に取り組んでいるところであり、引き続き、国内外の活力を取り込むことで、観光消費額の拡大を図り、地域経済の活性化につなげてまいります。
文化の振興
長崎県美術館は、平成17年の開館以降、「呼吸する美術館」をコンセプトに、水辺の森公園と調和し運河をまたぐ開放的な美術館として、多くの方々に親しまれ、本年2月には、総入館者数が700万人を突破いたしました。 こうした中、去る4月11日には、多くの関係者のご出席のもと、開館20周年記念式典を開催したところであります。 今後も、現在開催中であり、歴代の企画展の最多動員を更新した「金曜ロードショーとジブリ展」のほか、プラド美術館からゴヤの名画をお借りして開催する企画展や「皇居三の丸尚蔵館収蔵品展」などを実施することとしております。 引き続き、長崎県美術館が、本県の芸術文化の発展に寄与し、また、本県の魅力を広く発信していく文化活動の拠点として、県民の皆様に親しまれる美術館となるよう取り組んでまいります。
中国との交流
本年は、長崎県と中国との友好交流の懸け橋として重要な役割を果たしてきた中国駐長崎総領事館の開設40周年という節目の年であります。 県ではこれを記念して、去る6月4日、長崎市内において、呉江浩中国駐日本国特命全権大使をお招きし、祝賀会を開催いたしました。 その際、私は、これまでの交流促進のためのご尽力に対する感謝とお祝いを申し上げ、ご出席の皆様と意見を交わす中で、改めて、本県と中国との交流の歴史において中国駐長崎総領事館が果たしてきた役割の大きさを認識したところであります。 今後とも、中国駐長崎総領事館のご支援をいただきながら、長年にわたって築かれてきた本県と中国との絆が、さらに強固なものとなるよう、様々な分野での交流を推進してまいります。
日本産水産物の中国向け輸出再開にかかる日中合意
去る5月30日、農林水産省から、日本産水産物の中国向け輸出再開のために必要な技術的要件について、日中双方で合意に至ったことが発表されました。 令和5年8月のALPS処理水の放出以降、中国向け日本産水産物の輸出が全面停止している中、県としては、これまで国や中国に対し、停止措置の早期解除に向けた要請を積極的に行ってきたところであり、今般の発表は輸出再開への前進であると受け止めております。 引き続き、輸出再開に向けた動向を注視しつつ、関係機関と連携し、再開時の速やかな輸出に向けた調整等を進めてまいります。
核兵器廃絶に向けた取組
去る4月27日から5月3日まで、核兵器不拡散条約再検討会議準備委員会の開催に合わせ、徳永県議会議長とともにアメリカ・ニューヨーク市を訪問いたしました。 現地では、広島県やモンゴル国政府等との共催による安全保障と持続可能性などをテーマにしたシンポジウムを開催したほか、次代を担う「ナガサキ・ユース代表団」が核軍縮と核兵器廃絶に向けた新たな戦略を考えるイベントに参加し、議長からも平和に対する思いをお話しいただいたところでございます。 また、アントニオ・グテーレス国際連合事務総長やアメリカ合衆国、ロシア連邦、タイ王国などの各国軍縮関係者と面会したところであります。 その際、「長崎を最後の被爆地に」という県民の皆様の強い思いをお伝えするとともに、次期SDGsの目標に核兵器廃絶を位置付けることを目指して、各国の政府関係者が参加する組織体の立ち上げに向けた働きかけを行ってまいりました。 面会した方々からは、被爆80年を迎える中、国際社会において被爆県が果たす役割が、これまで以上に大きくなっていくことへの期待が寄せられたところであります。 また、広島県と連携して行っている持続可能性の観点からの核兵器廃絶に向けた取組についてご賛同いただくとともに、人材育成やサイドイベントでの本県との連携可能性に言及いただくなど、大変意義深いものとなりました。 県としては、今後とも、今回のNPT再検討会議準備委員会への参加によって得られた新たなネットワーク等も活用しながら、長崎市や広島県、関係団体等と連携のうえ、一日も早い核兵器廃絶と世界恒久平和の実現に向け、全力を尽くしてまいります。
ながさきピース文化祭2025の開催準備
「ながさきピース文化祭2025」の開催まで、残すところ3か月となり、成功に向けて市町や関係団体等と最終調整を行っているところであります。 9月14日にアルカスSASEBOで行われる文化祭の幕開けを飾る「開会式」については、先日、さだまさしさんをはじめとした出演者を発表するとともに、一般観覧者の募集を開始したところであり、大会の気運も一気に高まってまいりました。 そうした中、去る6月7日、させぼ五番街において開催した100日前イベントでは、本県の文化芸術を披露する各種ステージイベントを実施したほか、開会式に出演されるアンバサダーの長濱ねるさんと共に、私も文化祭を積極的にPRしてまいりました。 引き続き、本県が持つ文化の魅力が十分に感じられ、多くの皆様の心に残る文化祭となるよう、市町や関係団体等と連携し、開催に向けた準備に万全を期してまいります。
教育環境の充実と教育を支える人材の確保
子どもたち一人ひとりの個性に対応した質の高い教育や社会の変化に対応した学びを推進していくためには、多様な学びの場の提供や教育環境の充実のほか、教育を支える人材の確保が必要であると考えております。 このような中、令和5年度から大村市の県教育センター内に開設の準備を進めておりました長崎県遠隔教育センターについては、九州初となる遠隔授業の拠点として、去る4月11日に開所式を行ったところであり、今年度は離島半島部の小規模校9校に、情報や理科の専門科目などを配信しております。 県としては、この遠隔教育センター、愛称、「デクット」の活用により、地理的要因や学校規模にとらわれない、多様で豊かな学びの提供を推進してまいります。
石木ダムの推進
石木ダムについては、渇水や洪水などの自然災害から地域の皆様の安全・安心の確保を図るうえで必要不可欠な事業であり、早期完成を目指す必要があることから、工期内の確実な完成に向け、工事工程に沿って着実に工事を進めてまいります。 一方で、川原地区にお住まいの13世帯の皆様のご理解とご協力を得たうえで、事業を円滑に進めることが最善であることから、去る4月20日及び6月1日に川棚町において、石木ダムの技術的な疑問等に対する説明会を開催し、川原地区にお住いの皆様にもご参加をいただいたところであります。 また、佐世保市及び川棚町とともに策定を進めております水源地域整備計画については、昨年12月に素案の公表を行い、広くご意見を伺ったところであります。 今後、いただいたご意見や地元説明会の結果等を踏まえ、国へ計画を提出する予定としております。 県としましては、石木ダムの一日も早い完成に向けて、引き続き、佐世保市及び川棚町と一体となって、事業の推進に力を注いでまいります。
幹線道路の整備
県では、産業の振興や交流人口の拡大による地域の活性化、さらには強靱な県土づくりに向けて、高規格道路など幹線道路の整備を進めております。 去る4月1日に発表された今年度の国土交通省関係予算において、島原道路で唯一の未事業化区間である諫早市小野町から長野町間について、計画段階評価に着手されることとなりました。 これは、同区間の新規事業化、さらには島原道路全線開通に向けての大きな一歩として、大変喜ばしいことであります。 さらに、今回、島原半島地域における道路網について、計画の具体化に向けた検討を進めることが、国土交通省から示されたところであります。 この間、ご尽力を賜りました本県選出国会議員の皆様をはじめ、県議会並びに関係市の方々に対し、心から感謝申し上げます。 また、西九州自動車道の松浦佐々道路については、松浦から平戸インター間の今年度の完成供用に向け整備が進められるとともに、佐世保市江迎地区では江迎2号トンネルに着工されるなど、着実に事業が推進されております。 このほか西彼杵道路については、大串白似田バイパスにおいて、トンネル工事に向けた工事用道路の整備に着手するとともに、未事業化区間のうち長崎市長浦町から日並インター間の事業化に向けた環境影響評価の手続きを進めてまいります。 引き続き、産業の振興や地域の活性化に寄与する高規格道路の整備推進に全力で取り組んでまいります。
企業誘致の推進
企業誘致については、特に誘致競争が激しいアンカー企業の立地に適した大型の工業団地整備に向け、民間活用による整備を図るため、県と東彼杵町が連携し、公募しておりました事業者について、去る6月11日に、大和ハウス工業株式会社を優先交渉先事業者として決定いたしました。 今後、同社とスケジュールや整備手法等について、具体的な協議を進め、半導体など成長分野のアンカー企業誘致に向けた工業団地の整備に取り組んでまいります。 また、去る3月26日、兵庫県に本社を置く株式会社WaveTechnologyが、長崎市への立地を決定されました。同社は、情報通信関連機器の設計・開発を実施されており、5年間で15名を雇用し、電気自動車などに使用されるパワーエレクトロニクス機器の設計などを行うこととされております。 さらに、6月10日には、東京都に本社を置き、長崎市、佐世保市及び五島市に立地している株式会社ディーソルが、新たに島原市への立地を決定されました。同社は、5年間で100名を雇用し、医療関連企業向けのBPOサービスなどを行うこととされております。 引き続き、雇用の拡大と地域経済の活性化を目指して、地元自治体や関係機関と連携しながら、企業誘致の推進に力を注いでまいります。
文化財の返還
平成24年10月に盗難され韓国に持ち出された県指定有形文化財「観音寺の観世音菩薩坐像」が、去る5月12日に、対馬市の観音寺に返還され、同日、対馬博物館に収蔵されました。 当該仏像は、地域の人々により大切に守り伝えられてきた心の拠り所であり、無事に返還されたことは、大変喜ばしく、関係皆様のこれまでのお力添えに深く感謝申し上げます。 県としては、対馬博物館に収蔵された当該仏像をはじめ、本県の貴重な文化財の保存活用に、引き続き、尽力してまいります。
スポーツの振興
本年3月に開催されました「全国高等学校選抜大会」において、本県高校生が素晴らしい成績を収めました。 団体競技では、島原高校剣道部が、男子団体で悲願の初優勝に輝き、個人競技では、ウエイトリフティング競技男子 67kg級で諫早農業高校の田中彗斗(たなかけいと)選手が優勝を飾りました。 また、3月20日から23日まで行われた第62回全日本ボウリング選手権大会では、男子3人チーム戦で本県チームが優勝、個人総合においても福満亮(ふくみつりょう)選手が優勝を果たしました。 選手並びに指導に当たられた関係者の皆様のご健闘をたたえるとともに、引き続き、本県選手の活躍に向け、競技団体等と連携しながら、競技力の向上に取り組んでまいります。 プロバスケットボールチーム長崎ヴェルカは、2年目の挑戦となったトップリーグのB1において、26勝34敗の西地区6位という成績で今シーズンを終えました。 ハピネスアリーナを新たな本拠地とした今シーズン、ホームゲームの平均入場者数はB1の全24チーム中4位と、会場は毎試合、大きな盛り上がりを見せたところであります。 国内最高峰の舞台で戦い抜いた監督、選手、関係者の方々のたゆまぬご努力に対して、深く敬意を表しますとともに、熱いご支援をいただいた、県民の皆様方をはじめ、経済界、関係団体の皆様に心から感謝申し上げます。 地元プロスポーツクラブである長崎ヴェルカの存在は、県民に夢や感動を与え、地域の活性化に大きく寄与するものであり、来シーズンのさらなる活躍を期待するとともに、県としても、引き続き、市町や関係者、県民の皆様と一体となってしっかりと後押しをしてまいります。
次に、議案関係についてご説明いたします。 まず、補正予算でありますが、今回は、国庫補助事業の内示等に伴う事業費の追加、その他緊急を要する経費について編成いたしました。 一般会計58億4,775万1千円の増額 補正をしております。 この結果、現計予算と合算した本年度の一般会計の歳入歳出予算額は、7,406億526万8千円 となり、前年同期の予算に比べ、 50億7,248万9千円 の増となっております。 次に、予算以外の議案のうち、主なものについてご説明いたします。 第69号議案「知事及び副知事の給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例」は、私の政治資金等に係る一連の問題で、県政の混乱を招き、県民の皆様にご心配をおかけしたことに対し、深く反省し、心からお詫びを申し上げるとともに、私個人としての道義的責任を明確にするため、自らへの処分として、給料について、1か月間全額を減額するため、所要の改正をしようとするものであります。 第74号議案「長崎県立佐世保青少年の天地条例等の一部を改正する条例」は、長崎県立千々石少年自然の家の廃止及び県立青少年施設の安定した施設運営の継続のため、所要の改正をしようとするものであります。 第75号議案「長崎県営バス運賃等条例の一部を改正する条例」は、輸送サービスを継続して提供するため、運賃の見直しをしようとするものであります。 第76号議案「長崎県技能会館条例を廃止する条例」は、諫早市への移譲に伴い、長崎県立諫早技能会館を廃止しようとするものであります。 第85号議案は、長崎県収用委員会の委員の任命について議会の同意を得ようとするものであります。 委員といたしまして、 楠本愛氏 久村豊彦氏 を任命しようとするものであります。 いずれも適任と存じますので、ご決定を賜りますよう、よろしくお願いいたします。 なお、収用委員会委員を退任されます、山口雄二委員には、在任中、多大なご尽力をいただきました。この機会に厚くお礼申し上げます。 その他の案件については、説明を省略させていただきますので、ご了承を賜りたいと存じます。
以上をもちまして、本日提出いたしました議案の説明を終わります。 なにとぞ、慎重にご審議のうえ、適正なるご決定を賜りますようお願い申し上げます。