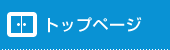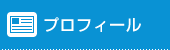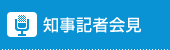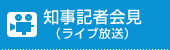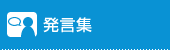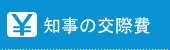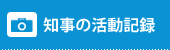長崎県ホームページ
パンくずリスト(現在位置の表示)
知事のページ - 長崎県知事 大石賢吾
令和7年2月14日 記者会見
●会見内容●
|
|
○広報課長 定刻となりましたので、予算の内訳のほうをお願いいたします。
○知事 よろしくお願いいたします。
令和7年度の当初予算編成の基本方針でございます。
基本的な考え方としまして、まず1点目に、長引く物価高騰への対応を上げております。やはり県民の皆様の生活を豊かにするためには、その基盤となります経済をしっかりと回していくことが重要であると考えております。今年度の経済対策補正予算と一体で、家計の負担軽減や事業者の皆様の経営改善等に資する施策をしっかりと講じてまいりたいと考えております。
次に、2点目にありますように、令和7年度は総合計画の最終年度でございます。ビジョンの推進と併せて、計画の総仕上げに向けて各種施策を積極的に展開をしていきたいと考えております。
そして、3つ目にございますように、次年度は被爆80年など様々な節目の年でもございます。「ながさきピース文化祭2025」や「ツール・ド・九州」など、大型イベントも本県で開催をされます。こうした区切りや節目を契機といたしまして、県勢のさらなる発展を図っていきたいとの思いから、令和7年度の当初予算は、国内外の方々とのつながり、これを広げて、次期総合計画につなげるための予算として編成をさせていただきました。
具体的には、後段にお示しをしておりますとおり5つの重点テーマとして、「こども」、「ブランディング・PR」、「産業」、「安全・安心」、そして「現下の諸課題への対応」という5つの重点テーマを掲げて予算を計上してございます。これによって物価高騰などの直面する課題にしっかりと対応しつつ、経済活性化や安全・安心の確保など、本県の発展のために必要な施策を力強く推進をしていきたいと考えております。
2ページをお開きいただきまして、上段の令和7年度当初予算の規模についてでございます。
令和7年度一般会計当初予算は7,347億円でございます。これは6年連続の7,000億円台を確保している状況でございます。また、職員給与費を除きますと、前年比49億円の増となってございまして、防災・減災対策の推進、子どもや福祉分野におけるきめ細やかな対応と、半導体をはじめとした成長分野への取組支援、また、農林水産業の振興といったことなど、各産業の活性化に力を注いでいきたいと考えております。
そして、下のほうに書かせていただいておりますのは、今年度の経済補正予算と令和7年度の当初予算の一体的な編成のイメージをお示しをしたものになります。
補正予算につきましては、その多くが令和7年度での執行となりますことから、相乗的な効果が発揮されますように、物価高騰対策を含め、令和7年度当初予算と一体的に推進をしていきたいと考えております。
3ページから7ページにつきましては、歳入歳出の動き、また、基金、県債の状況となってございます。これは事前に財政部局からご説明があったということを伺っておりますので割愛をさせていただきたいと思います。
8ページをお開きいただければと思います。
8ページ以降は、国の重点支援地方交付金を活用いたしました追加物価高騰対策をまとめたものになります。長引く物価高騰によって影響を受けております県民の皆様、また、事業者、生産者の方々に対しまして、国の交付金等を活用しながら県民生活を下支えをして、県内経済活動を活性化させるために必要な支援をしっかりと講じていきたいと考えております。各事業の内容につきましては、次のページ以降、ご説明をさせていただきたいと思います。
9ページになりますが、ここは生活者支援の取組となってございます。
[1]と[2]につきましては、子育て世帯の負担軽減、家計負担軽減を図るために、学校給食費等の一部を支援するものになってございます。そして、[3](3)につきましては新規事業となってございますけれども、県民生活の下支え、また、事業者等の売上拡大を目的としまして、市町が行うプレミアム商品券の発行の後押しをさせていただくものでございます。
10ページから12ページにつきましては、事業者の方ほうの支援となってございます。農業、水産業や中小企業、公共交通事業者など各分野の状況に応じまして、省エネや生産性向上等の取組を支援させていただくものとなってございます。
13ページ以降になりますけれども、ここでは令和7年度の当初予算となってございます。冒頭ご説明しました5つの重点テーマに沿って、主な取組をご説明をさせていただければと思います。
14ページをお開きください。
こちらは重点テーマ1になりますけれども、「こ子どもが夢や希望を持って健やかに成長できる社会の実現」に資する取組となってございます。この14ページにおきいたしましては、その中でも主な新規・拡充の内容をまとめたものになります。次のページ以降では、これらを中心にご説明をさせていただければと思います。
まず、15ページ、「こども場所」の充実や支援体制の強化」を図るビジョン事業になります。これまで取り組んでまいりました官民連携の仕組みづくりをさらに推進するとともに、新たに子ども施策を推進するために、「長崎県こども未来応援基金」を創設をして、「こども場所」づくりの支援を充実させていくものでございます。具体的には、官民ネットワークの構築、また、中間支援組織の設置等と併せまして、この基金を活用して、こども食堂など安全・安心な居場所の立ち上げ、それに加えてモデルとなります体験提供を支援するほか、市町と連携したこども食堂の運営への支援や、アンケート等により子どもの意見を聞く機会を設けるなど官民一体となって、子どもが主役となれるような、そのような長崎県の実現を目指していきたいと考えております。
16ページになりますけれども、「こども場所」の充実と「こども時間」の確保」といたしまして、[2]番目と[3]番目につきましては、近年、増加傾向にございます不登校児童生徒への支援体制強化を図るものとなってございます。
具体的には、[2]につきましては、市町と連携をいたしまして、県内の小中学校におけます校内教育支援センターの設置促進でありましたり、指導員の配置拡充を行うものでございます。[3]になりますけれども、こちらのほうでは、児童生徒の心のケア等サポートの充実のために、不登校児童生徒への支援に特化したスクールカウンセラーの配置を支援するものでございます。[4]と[5]番につきましては、「こども時間」の確保のために、共家事・共育ての周知啓発であったり、ひとり親家庭の生活時間の把握等を行うものでございます。
17ページ上段のほうにつきましては、「安心して結婚、妊娠・出産、子育てできる環境の整備」としまして、[2]につきましては、新たな取組といたしまして、産後ケアを希望する全ての方々が安心して利用することができるように、利用者と施設間のマッチング機能等を備えたアプリを導入すること。それに加えて、県内のどこでも、希望する施設を利用できるような仕組みを構築していくといった取組になります。[3]につきましては、子育て環境を整えるために必要な保育人材の安定的な確保に向けて、新たに若年層への幼児教育・保育の現場の魅力発信であったり、DX・ICT化による保育現場の負担軽減を図るような取組となってございます。
下段のほうになりますけれども、「教育環境の充実と教育を支える人材の確保」といたしまして、一つ書かせていただいておりますけれども、長崎県の遠隔教育センターを令和7年度から開設をいたしまして、地理的条件に関わらず遠隔授業であったり、メタバースの活用といったことなどによって、子どもたちの興味や関心、進路希望等に応じた多様で豊かな学びを提供していきたいと考えております。
続きまして、18ページの[2]番になりますけれども、これからグローバル社会において求められる異なる言語であったり文化、価値への理解、コミュニケーション能力の向上を図って、グローバル人材の育成を目指すものでございます。一番下、[5]番目になりますけれども、教員の業務負担軽減につながる取組等を促進をしていきたいと思います。こそのことによって、教育環境の改善であったり、教育を支える人材の確保、これに努めていきたいと考えているところでございます。
19ページからは2つ目の重点テーマになります。「戦略的なブランディングによる国内外の多方面から「選ばれる長崎県」の実現」に資する取組となってございます。これも1つ目の重点テーマと同じで、その中でも主な新規・拡充内容について、ここでまとめさせていただいております。
20ページをお開きください。
「多様な地域資源等を活用した交流人口・関係人口の拡大」といたしまして、[1]つ目に書かせていただいておりますのは、本県のイメージ向上につながる「長崎ブランド」の構築を行うことを目的とした事業でございます。そして、下の[2]つ目になりますけれども、こちらにつきましては、市町と連携をいたしましたアニメツーリズムを推進するビジョン事業になります。これは、現在取り組んでおりますマニア向けのコンテンツづくりや情報発信に加えまして、新たに本県が舞台となったアニメ作品を活用した聖地巡礼ツアー等の取組を市町と連携をして展開をしていきたいと考えております。
21ページ、上から2つ目、[4]番になりますけれども、今年度実施をいたしました調査の結果に基づきまして、モニターツアーの実施、また、ハブ人材の育成など受入れ基盤づくりによって、デジタルノマドの誘致を推進していくものでございます。その下、[5]番につきましては、日本遺産「国境の島」認定10周年になりますけれども、これを契機に、関係市町において講演会や周遊イベント等を実施をいたしまして、さらなる認知向上、そして誘客を促進していきたいと考えております。下から2つ目、[6]番になりますけれども、県内のインフラ施設を観光資源として活用していきたいということでございますけれども、その活用するための地域における受け皿づくり等を進めて、魅力ある観光コンテンツとして創出をしていきたいという取組になります。
22ページになりますけれども、こちらは「インバウンド誘客の拡大と友好交流・平和発信の促進」と帯を書かせていただいております。
[1]番に関しましては、新たに海外のOTAサイトを活用いたしまして、本県の観光、また、食の魅力発信など、インバウンド誘客の拡大に向けたプロモーションを実施をするものになります。そして、[2]番目になりますけれども、国際定期航空路線について、上海、ソウルの2つの既存路線、このれを利用拡大をしていきたいということ。そして、加えて新規路線の誘致にも引き続き取り組んでいくというものになります。
そして[4]番、今年は被爆80周年になります。被爆80年事業でございます。節目の年に当たりまして、長崎市や広島県、関係団体等と連携をしまして、被爆地から世界に向けた平和発信を促進するとともに、次代を担う平和人材の育成、地域や世代を超えた平和教育などに取り組んでいきたいと考えております。次期SDGsの目標に核兵器廃絶が位置づけられるように、共感いただいた団体によるイベント等を支援するほか、若い人たちをはじめとする人材育成等にも積極的に引き続き取り組んでいきたいと考えております。
23ページになりますけれども、こちらは「本県の豊かな食の魅力発信と賑わいの創出」といたしまして、[1]番は、食の賑わいの場の実証や食文化の魅力発信を行うビジョン事業になります。今年度実施中の調査内容を踏まえまして、次なるステップといたしまして、県民や観光客など誰もが本県の食を買って味わえるような食の賑わいの場の創出に向けまして、食の賑わいの試行、そして実証等を推進をしてまいりたいと考えております。
24ページ、[2]から[4]番目のものにつきましては、農林水産物等の輸出・販路拡大を図る取組を部局横断で実施をしていきたいと考えております。そして一番下、[5]番目につきましては、県産品の魅力発信に加えまして、実際に購入できるように、新たに民間のECサイト上に県の特設サイトを開設をするものとなります。
25ページからは、大型イベント等を通じた交流拡大の推進といたしまして、[1]のつ目「ながさきピース文化祭2025」や、[2]つ目の「ツール・ド・九州」の開催に向けて、市町や関係団体等と連携して着実に準備を進めていくということ、また、実施も進めていくということです。[3]につきましては、4月から10月までの半年間、開催をされます大阪・関西万博につきまして、九州7県合同で観光や物産等を発信するブースを設置をいたします。そのほか関西の主要商業施設等において、本県独自のPRを実施をさせていただくなど、年間を通じて、関西エリアにおける本県のさらなる認知度向上に向けた取組を、これも部局横断的に連携を強めて展開をしていきたいと考えております。
26ページ、[4]につきましては、我々の長崎県がに抱える課題の一つとして西九州新幹線がございますけれども、これについて、大阪・関西万博も契機として県外に向けて情報発信等の充実を図るものになります。そして、[5]番目と[6]番目につきましては、プロスポーツクラブと連携したスポーツ振興の取組であったり、バスケットBリーグのオールスターゲームがありますけれども、この機運醸成等を図るものとなってございます。
そして、27ページからは3つ目の重点テーマになりますけれども、「最先端のテクノロジー活用やイノベーションによる力強い産業の実現」に資する取組をまとめさせていただいております。これも1つ目と2つ目と同じように、ここ、一つのページの中に主な新規と拡充内容をまとめさせていただいております。
28ページをお開きください。
まず、1つ目、「新たな基幹産業の育成、新技術の社会実装とチャレンジの促進」といたしまして、[1]つ目につきましては、国内投資が非常に活発化をしてございます半導体関連産業につきまして、大手半導体関連企業からの受注獲得を目指して、県内サプライチェーンの構築・強化や、企業人材の育成・確保を集中的に支援をしていくものでございます。そして、一番下、[3]番目になりますけれども、海洋エネルギー関連産業に加えまして、新たに水素関連産業において参入可能性調査を行いながら、サプライチェーン構築に資する企業間連携の取組を支援するものとなってございます。
29ページは、スタートアップに関連する支援になります。令和7年度は、投資家とのマッチングイベントでございます「ミライ企業Nagasaki」がございますけれども、この充実を図るために、新たに首都圏の交流拠点等と連携をいたしまして、県外からのスタートアップの呼び込み強化、そして、大企業等との取引拡大に向けた支援を行っていきたいと考えております。
30ページ、これはイノベーション分野のビジョン事業になりますけれども、国家戦略特区の指定を踏まえまして、ドローンの活用による地域課題への対応等を図るため、ドローンへの理解を深めるためのイベントの開催、そしてオペレーター育成、ドローンの社会実装に向けた取組の支援といったことも推進をしていきたいと考えております。
31ページ、上段になりますけれども、[6]番につきましては、県内におけます自動運転バスの社会実装に向けて、長崎空港から新大村駅間におきまして実証運行や検証等を推進していくものになります。
そして、下段になりますけれども、「持続可能な農林水産業の推進」といたしまして、我々、長崎県にとって非常に重要な基幹産業でございます第一次産業の振興策を上げてございます。[1]につきましては、農業の分野におきまして、気候変動に強い産地づくりを進めるために、気候変動リスクに対応した品種であったり技術等の開発・実証、資機材の導入支援等の取組を推進していくものとなってございます。
32ページの[4]番につきましては、畜産業におきまして、肉用牛の産地の発展に向けて、繁殖能力の高い雌牛の導入を促進するものとなっております。そして、[6]番になりますけれども、養殖業において、近年、頻発をしてございます赤潮への対応など課題解決に向けて、民間のアイデアを活用しながら技術開発、そして実証を推進していく事業となります。
33ページ、上段になりますけれども、[7]番につきましては、新たに産地における中核的な養殖業者による先端技術の導入、そして販売力強化といったことを目的として、養殖産地の成長を支援していくものでございます。
下段になりますけれども、各分野においてお声をいただいております産業人材等の育成、そして確保に向けた取組になります。[1]につきましては、県と市町が共同で外部デジタル人材を活用できる体制を構築していくものになります。そして、[2]つ目につきましては、セキュリティ・デジタル分野におきまして、大手セキュリティ企業と県内企業とのマッチングなどを行いながら、事業化支援や人材育成の取組を推進していく事業となります。
34ページ、[4]番と[5]番につきましては、高校生や大学生の県内就職の促進に向けた取組でございます。
そして、[6]番からは、外国人の確保・育成に関する取組をパッケージで掲載をさせていただいております。[6]番につきましては、企業向けの相談窓口や受入促進セミナーなどのほか、新たにモデル3市におきまして、企業が実施をいたします受入環境整備への支援等に取り組む事業となっております。
次のページ、[7]番に関しましては、IT人材に関しまして、これはフィリピンからの受入れになります。そして[8]番につきましては観光人材でございますけれども、こちらは現在、ネパールを対象国としておりますけれども、ここを拡大していきたいと、それに向けた取組になります。[9]番、[10]番につきましては、介護分野と農業分野について、新たに外国人材受入れのための居住環境整備等を支援していくものになります。そして、最後[11]番に関しましては、地域における日本語学校の体制強化、内容の充実を図る事業となっております。
36ページからは、4つ目の重点テーマになります。「全世代が豊かで安全・安心に暮らせる持続可能な社会の実現」に資する取組となってございます。
37ページをお開きください。医療・福祉・介護サービスの分野になります。[1]つ目になりますけれども、現行のドクターヘリに加えまして、新たに、病院企業団が有しております離島等の医療連携ヘリ、RIMCAS(リムキャス)というものがございますけれども、これを運航しない日に2機目のドクターヘリとして活用することによって、救急患者の搬送体制を強化していくものになります。[2]つ目につきましては、常勤医師のいない離島の公立診療所におけますICTの活用や普及・拡大を図る新規の事業となっております。
38ページ、[4]につきましては、医師会が設置をいたします看護師等養成所の運営に係る支援の充実を図るものとなっております。[5]番目と[6]番目につきましては、不足をいたします病院薬剤師や離島の歯科衛生士の確保に向けて、新たに県独自の奨学金返済支援制度を創設をするものとなっております。そして、[7]番につきましては、国の基本計画に沿った認知症に係る県計画の策定に向けて調査等を実施するものになります。
39ページ、[8]番になりますけれども、これにつきましては、発達障害の診療等に取り組もうとする地域の小児科医などに対しまして必要な研修等を実施をして、発達障害児の早期診療、早期療育を促進をしていくものとなっております。[9]番につきましては、透析患者の負担軽減に向けて、新たに低所得者を対象に、通院にかかる交通費の助成制度を創設するものになります。[10]番につきましては、法律の施行を踏まえまして、DVや性被害等の困難な問題に直面する女性への支援を実施するものになります。
そして、下段のほうには、誰もが健康で自分らしく暮らすことのできる社会づくりの推進といたしまして、[1]、ながさき健康づくりアプリの「歩こーで!」の一層の活用など、県民が主体的に健康づくりに取り組むことができる環境を整備をしていくという事業になります。
次のページ、[2]になりますけれども、これは高齢者の皆様の社会参加促進に向けまして、セミナーであったり地域貢献活動の実践講座、これを開催をさせていただきたいと思っております。そして、一番下、[5]につきましては、動物殺処分ゼロプロジェクトの取組でございますけれども、人と動物が共生できる住みよい社会づくりの実現を目指しまして、動物愛護管理センターの整備や地域猫活動に係る野良猫の不妊化手術支援などを実施をしてまいります。
41ページは、県民の安全・安心を守る社会基盤の整備と脱炭素社会の実現といたしまして、[1]、今年度実施をいたしました予備調査を踏まえまして、海域活断層の詳細調査や過去に行った本土地区の活断層調査の見直しによる地震アセスメントの実施等を行うものになります。
また、併せまして2月補正では、国の交付金を活用いたしまして、トイレカーの導入であったり、避難所の生活環境の改善に係ります資材の備蓄、災害時のヘリコプター離発着のための適地の調査を実施をいたします。こうした取組によりまして、防災・減災対策のを充実、強化を図っていきたいと考えております。
42ページの[3]につきましては、近年の自然災害の頻発化、激甚化を踏まえまして、5年間延長されました国の緊急浚渫推進事業債などの有利な財源も活用しながら、安全・安心な県土づくりを引き続き推進をしていくものとなっております。下の[4]番につきましては、脱炭素社会の実現に向けて、省エネ・再エネ等の取組を推進するものになっております。
そして、43ページからは最後の重点テーマになりますけれども、「現下の社会経済情勢を踏まえた諸課題への対応」ということでまとめさせていただいております。
44ページは、「地域コミュニティを支える中小事業者等に対する支援」といたしまして、[1]、今、県内の企業者の方々、本当に物価高騰等、様々なコストが上がる中で、非常に厳しい状況で経営をしておられます。そういった中で、商工団体の経営指導体制の強化を図ることによって、小規模事業者の業務効率化や売上拡大等を支援していく取組となります。そして、[2]番につきましては、中小の食料品製造事業者の生産性向上、また、収益拡大に向けた取組等を支援するものになります。[3]番につきましては、離島地域に加えまして、新たに本土の条件不利地域等で生産・加工された産品の販路拡大や、生産者や事業者の商品開発、生産拡大等を支援する事業となっております。一番下の[4]になりますけれども、市町と連携をいたしまして、「こども場所」づくりといったことなど地域課題の解決等につながる商店街の取組を支援をさせていただくものになります。
45ページにつきましては、国境離島交付金の活用状況でございます。引き続き、これも最大限活用しながら予算を編成をしてございます。
46ページのうち、[3]につきましては、離島の海上高速交通の維持・確保のために、老朽化をいたしました高速船ジェットフォイルの更新を引き続き支援をしていくものになります。[4]につきましては、交通事業者等の人材確保の取組や市町によるコミュニティ交通への転換、これを支援するものになります。
47ページにつきましては、IRの取組等を活かした県北地域の振興としてまとめさせていただいております。[3]につきましては、西海橋公園の官民連携によるリニューアルの検討や、県北地域におけますガーデンツーリズムを推進していくものになります。そのほかにつきまして、ツール・ド・九州がございますけれども、この開催のほか、テーマで説明した取組を再掲をさせていただいておりますけれども、説明は割愛をさせていただきたいと思います。
このほか、産業基盤の充実強化といったことなど、当初予算計上事業の執行において、県北地域を含めて実施内容等を選定の上で、関連施策を推進をしていきたいと考えております。今後も引き続き、IRの取組で目指してきました交流人口の拡大や産業振興などの考え方を継承して、その知見や観光資源を活かして、県北地域の活性化はもちろんでございますけれども、その効果を県全体へと拡大をしていけるように取組を進めていきたいと思っています。
48ページは、新しい地方経済・生活環境創生交付金の活用状況でございます。これも引き続き、最大限活用しながら予算を編成してございます。
それ以降、49ページ以降につきましては、2月補正予算の一覧や当初予算の主な取組を分野別にまとめた参考資料となってございますので、これ以降の個別の説明は割愛をさせていただきたいと思います。
冒頭、私から予算に関する説明は、一旦、以上とさせていただきます。
○広報課長 それでは、幹事社のほうから質問をお願いいたします。
○記者(読売新聞社) 私から、まず幾つか質問させていただきます。
今回、予算編成に当たって5つの重点テーマを設けていて、もちろんここに優劣はないと思うんですけれども、トップに「こどもが健やかに成長できる社会の実現」ということで、知事、常々、折に触れて子ども施策の重要性というのはずっと説いていたと思いますけれども、改めてここに込めた思いというのを具体的にお聞きしてもいいでしょうか。
○知事 子ども分野についてですかね。子ども施策、分野については、やはり県政の基軸として取り組んできたことでございます。これまでビジョンでも取り組んできましたけれども、やはり子どもがまず主役になれる、そういった環境をつくっていきたいと思っております。それに向けて中間支援組織であったり、今回、基金の創設も目指していくことになりますけれども、まずはそういったこれまでの取組をしっかりと次につなげていけるように、実際にこの検討したものが、新しく中間支援組織として体制をつくっていくと、構築をしていくと。それによって「こども場所」が、これは県だけではつくっていくことは難しいですけれども、様々な主体を巻き込んでいきながら、ご協力をいただきながら一緒に、実際に子どもが主役となって、安全・安心に過ごせるだけでなくてチャレンジができるような、体験ができるような、そういった場所を数多くつくっていけるような、そんな取組につなげていきたいと考えております。
○記者(読売新聞社) 追加で、今お話しされていたことと重複するかもしれませんけれども、先日の総合計画の策定に向けた懇話会でも、例えば、直接的に子どもを支援するという部分だったり、子どもに関わる大人を支援するという部分だったり、いろんな角度があるという話がありましたけど、そういった点で何か気を配った点、工夫した点などはありますでしょうか。
○知事 そうですね、これまで県政で本当にいろんな方々の声を聞きながら、もちろん議論をしてきましたけれども、その中で取組を振り返る中で、子育て支援としては、先ほど言った後者の側ですね、子どもを育てる側、子どもを支援していく者に対する充実といったものも本当にきめ細やかに進めてきていただいておりました。その子どもに焦点を当てたといったところについては、もちろんやっていただいておりましたけれども、まだまだやれることがあるんじゃないかなというふうに感じておりましたので、そこについてはやはり両方、どちらに偏るわけではなく、子どもがやっぱり主役になってチャレンジができる、安全・安心に暮らせる、過ごせる、そして、長崎県に生まれたからといって何か諦めることがないようにと、その居住地に限らず、本当に自分がやりたいことを目指していける、学べる、そういった環境を目指していくために、それにつながるような取組を今、進めさせていただいているというところです。
あと、子どもを支援する側ですね、教育であったり親御さんであったり、いろんな方々がおられますけれども、そちらに対する支援といったことも、これも県だけでは難しいですので、基礎自治体であったり関連団体等と連携を重視しながら、そういった取組を進めていけるように予算編成したところでございます。
また、その中で、先ほど触れませんでしたけれども、県として、額はそれほどそんな大きなものではないかもしれませんけれども、今回、産後ケアですね、県内どこでも使えるようにということで取組をさせていただいております。これは、まさに皆さんの協力を得て、県だからこそ調整をしてできたこと、進めていけることなのかなと思っております。こういったことを充実させていきながら、子どもも伸び伸びとチャレンジできるような、そういった環境をつくっていきたいと思いますし、それを支える側も、過度な負担がどこかにしわ寄せが寄っていくわけではなく、みんなで、県民総ぐるみで育てていける、見守っていけるような、そんな長崎県を皆さんと一緒につくっていけたらと、そう思って今回編成をさせていただきました。
○記者(読売新聞社) 私から最後に、話変わりますけど、基本的な考え方にもあるとおり、今年はいろいろな節目があり、周年行事があって、ツール・ド・九州など大型のイベントもあり、県として非常に好機だとは思うんですけれども、一方で、それが何か看板だけになってしまわないかというところが気になるところで、いかにその周辺で有効な施策を打って効果を波及させていくのかというところで、そこが知事の腕の見せどころだと思うんですけれども、一つ具体的に、特に空港50周年でお聞きしたいんですけど、パスポートの取得補助とかPRイベントとかありますけど、もう少し詳しく、それを県全体の観光振興とか経済活性化にどうつなげていくのかという考えが何かあればお聞きしたいんですけど。
○知事 空港50周年につきまして、本当にいろんなイベントが1年間、全ては私も把握できてないですけども、関連したイベントも含めていろんなものが行われていくと思っております。そういったことを県としては、やはり広域行政でございますので、まず受入れをしっかり促進をしていくことで、施設として、窓口としてですね、関係者、民間も含めて協力をいただきながら、本当に入り口、窓口というのは、来ていただく観光客の方々との接点の場だと、タッチポイントだと思いますので、そういったタッチポイントをしっかりと有効活用していくと、今まで以上に活用していくという意味でも、その役割といったものを引き続き検討、可能な限りいいものにしていくといった取組は必要だと思っています。
加えて、空港から入ってきていただいた、空港だけではありませんけれども、窓口から入ってきていただいた方を、いかに県内各地に送客していくかという観点も非常に重要だと思っています。これは、決してモビリティだけではなくて、受け皿となる、消費をしていただく、消費ということは恐らく満足度につながると、そういう求め、需要があって消費をするわけですから、そこは消費が生まれるということは、それだけ満足度が高まる可能性が上がっていくと思いますので、そういった環境、宿泊、食、そして体験だったりとか、そういったものを広域的に、みんな底上げをしていきながら、長崎に来ていただいた方に、「やっぱり長崎っていいな」とか、「また来たいな」とか、もしかしたら「住みたいな」とか、そう思っていただけるような、そんな取組を一緒にやっていきたいなと。
ですので、長崎空港50周年といったこと、そのイベントが単発で終わらないようにという観点は非常に重要だと思っています、これは空港だけではなくですね。そういったことを様々、本当にいろんな角度でのイベントが起こっていきますので、その都度その都度、キーとなる主体と連携をして、広域行政としての先ほどの観点を踏まえた支援といったものを、もちろんしっかりとやっていきたいと思っています。
○記者(読売新聞社) 私からは以上です。
○記者(NIB) 空港の関係で私からも伺います。先ほどの長崎空港の50周年に絡んで、今回、予算の中で国際航空路線の利用促進とありますけれども、先ほど新規路線の誘致でも見据えたいという話もありました。具体的には、多分まだ検討中だと思うんですけれども、インバウンドとしてどのあたりを見据えていらっしゃるのか。そして、どういう客層をですね。この前も韓国、中国の路線あれが復活して盛り上がった点もありましたし、その点を見据えて展望を教えてください。
○知事 これはもう本当に、一概には言えませんけれども、やはり今おっしゃってくださったように、地域性もありますし、また消費するところで、来ていただく方々の層、ターゲット層というものもまたばらばらだと思います。
長崎県は、よく言われるのがアジアに非常に近いということ、西の端にありますので、そういったアクセス性のよさというところも重要視していかなくちゃいけないと思っています。また、それに加えて、今、上海、ソウルありますけれども、それ以外の例えば観光地と結ばれるということもすごく大切ですけど、そのつながる先がハブであるとか、そういった非常に機能も分かれることになると思いますので、そういったことをその時の情勢に合わせて、また、実現可能性ですね、そういったところも競争が非常に高いですので、そういったことを踏まえて総合的に実現可能性があるところを攻めていくということになると思います。
○記者(NIB) ありがとうございます。続いて、こどもの居場所、まさしく「こ子どもの場所づくり」の関係ですけれども、未来応援基金を創設されるということなんですが、先日のレクでもちょっと質問もあったんですけど、改めてその基金を創設して対応するというその意味はどういった点にあるんでしょうか。
○知事 まず、県としての大きな目的の一つとして、もちろん財源をしっかりとつくっていくことも重要だと考えています。もちろん一般財源でしっかりと捻出をしていくということも大事ですけれども、一般財源だけに、これは子どもに限ったわけではありませんけれども、様々な事業、課改題を解決していくために、その財源をつくる視点というものは非常に重要だと思っています。で、その弾力的な運用ですね、活用方法といったことも非常に重要だと思いますので、そういった観点から、基金といったことは、一つ手段になり得るかなと思っています。
加えて、この財源をつくった先でございますけれども、やはり「こども場所」づくりにおいては様々な課題がございますので、そこに対する経費についてしっかりと捻出をできるような体制をつくっていきたいと思います。
これについて、これからの取組になりますので、それはやりながら、またその状況を踏まえて、できる限りいい形にということになっていくかと思いますけれども、これまで子ども施策に対して応援をしたいと、協力をしたいとおっしゃってくださる企業であったり個人であったり、そういった方々のお声も聞いてございます。一定存在をしているところでございますので、これはもう、そういった企業の方々、個人の方々に幅広くお声をかけていくこと、そしてまた加えて、例えばふるさと納税とか、そういったことも絡めて連携をしていきながら、しっかりと機能するような基金にできればと考えています。
○記者(NIB) あと、県北振興のIRですね、IRの取組を活かした県北地域の振興の観点でちょっと伺いたいんですが、県北振興の思いというのは常々おっしゃっていますが、イベントですね、今ここにあるのは基本的には、西海橋公園のところは個別で出ていますが、そのほか再掲という点でちょっと、何でしょう、県北振興に向けての改めての考えというかですね、今ここに4個ありますが、そのほかの部分であれば、展望をちょっと伺いたいなというのがあります。
○知事 そうですね、県北はやはりIRで目指してきたことで様々、連携だったりとか関係者の思いが一致しているところであるとか、強みはあると思っております。そういったものをしっかり形にしていく、実現していく、実現につなげていくというのは非常に需要だと思っておりますけれども、ここに載せております「ツール・ド・九州」であったりとか食の賑わい、また西海橋とかツーリズムですね、そういったところもありますけれども、これ以外にも、もちろんこういったところは県北で起こっていくような、分かるようなメニューということで分かりやすくまとめさせていただいておりますけれども、これ以外にもやっぱり産業振興であったりとか、周遊も観光もそうですけれども、そういったところも全県下で行いはしますけれども、ここも県北も含まれてきますので、そういったところでやっぱり県北の強み、資源を活かした、そういった県北の活性化といったところには、関係者と関係市町も含めて連携をしてやっていきたいと思っています。
○広報課長 では、ほかに予算につきましてご質問のある方、すみません、挙手をお願いいたします。
○記者(NCC) 知事、1期目の仕上げの年でもあるかと思います。今回の予算に込めた思いについて、改めて聞かせてください。
○知事 思いは先ほどからずっとしゃべらせていただいたところでございますけれども、やはりおっしゃるとおり最終年になりますので、今までの経験も踏まえたりとか、今までと違う観点もあったりとか、そういったものはありますけれども、大きくはこれまでと変わらず、しっかりと目指してきたもの、皆さんと練り上げてきたものをしっかり実現していけるような、そういったものにしていく必要がありますので、そこは実現可能性とか、よりバランスのとれた、より発展性のあるといった観点で編成をさせていただいたつもりでございます。
また、今、少し経済対策補正のほうでも触れましたけれども、やっぱり経済的な社会情勢が非常に厳しい中で、本当にきめ細やかに、また補正も含めてスピーディーに対応しなくちゃいけないところもございます。そういったところももちろん配慮、配慮といいますか、しっかりと考えをめぐらせて予算編成をさせていただいたところでございます。
具体的にお話ししますと、まず一つ目を挙げると、やはり長引く物価高騰ですね。1つ目、一番初めのところで3つ挙げましたが、そのうちの一つとして挙げさせていただいておりますけれども、そこにしっかりと対応していくといったこと、補助もさせていただいておりますし、それに加えて、例えば消費であったらプレミアム商品券のものもございます。そういった消費拡大であったりとか生産性向上に向けた取組といったものも2月補正として上げさせていただいて、当初と一体となって予算をしております。
2つ目、子ども分野は先ほど申したとおりですけれども、やはり子どもは長崎県の未来ということをずっと申し上げさせていただきました。我々も年を取っていきますけれども、やっぱり世代が替わっていく中で、未来の長崎県を支えていくのは今生きている子どもたちだと思います。それだけではなく、外から来てくれる方もいらっしゃるかもしれませんが、その方々が、本当に予測するのが難しい社会をしなやかに生き抜いて活躍をすると。
今、技術開発がものすごくて、進歩がものすごくて、10年後、20年後、30年後、10年後はまだわかるかもしれませんが、30年後の未来はどうなっているのか、非常に予測が困難になっている状況かと思います。そういった中でもしっかりと対応能力があって、地元、ふるさとを愛して、そういった子どもたちが育っていくと、そういった環境は引き続き推進していけるように、みんなで、教育だけでやるんじゃなくて、やっぱり地域とか県民みんなで育てていけるような、そんな環境を目指して予算編成、中間支援組織、基金等もお話ししましたけれども、そういったことを意識して編成をしてございます。
それ以外も本当に重要でございますけれども、医療の提供体制、安全・安心の対策、それに加えて、いろんな、全世代の方々がどこに住んでいても安全・安心に暮らせるようにという思いもしっかり込めたつもりでございます。ですけれども、そういった今までの取組をは推進していくことに加えて、一つ特に申し上げさせていただくとすれば、やっぱり今、冒頭で申し上げた経済ですね。
いろんな取組を進めていく上で、人口減少もそうですけれども、やっぱりしっかり所得を上げる、経済を回していくということは非常に重要になると思っております。ですので、半導体にも触れましたし、それ以外の成長産業も今回支援をしっかりとさせていただくと、また、観光もそうですし、我々の長崎県の大切な基幹産業である一次産業、これも本当に今、気候変動等で大変なところもありますけれども、その中でもしっかりと伸びていくと、生産者の方々が頑張った分だけしっかりと収入につながっていくような、そういった状況をつくっていかなくちゃいけませんので、そこはみんなで知恵を出しながら、連携してやっていけるようなことを意識をして事業を組み立てたつもりでございます。
最終年度だからということでどうこうあるわけではありませんけれども、しっかりと今の現状を捉えて、これまでの取組を踏まえて、今、県がやるべきこと、それを意識をして予算編成を行ったつもりでございます。
○記者(西日本新聞社) ちょっと先ほどの質問と重なるところもありますが、最終年の4年目であったり、総合計画の5か年の5年目というところで、これは昨年度の事業数は154件、新規、拡充があったものが、今回80件弱と、およそ半減になっているように見受けられます。その点について、どういった要因があるというふうに思われますか。
○知事 事業数といったことはあまり意識はしていなかったんですけれども、でも、今考えると、結構連携をして取り組みましょうということを庁内挙げてお話をしてきました。議論も深めてきたつもりでございます。ですので、もしかするとですけれども、しっかりと見てみないとわかりませんが、今まで2つに分かれていたものが、もしかすると3つが2つとか、2つが1つとか、そういったこともあったかもしれません。
○記者(西日本新聞社) 分かりました。
○記者(長崎新聞社) よろしくお願いします。基本的な考え方のことでお尋ねですが、前回、今年度の予算発表の時は、ビジョンを前面に出したような形だったかなと思うんですが、今回の基本的な考え方を見ると、補正予算も含めてでしょうけれども、物価高騰への対応だとか、いわゆる経済活性化の部分で、こういったことを前面に出されていますけれども、このあたり、経済活性化というのを前に出しているところの狙いというのを改めて教えてください。
○知事 前、後ろというほどではなく、そこまで、どれも大切なんですけれども、先ほどNCCさんにお答えさせていただいたとおりで、やっぱり今、本当に厳しい状況の中で、賃上げであったり物価高騰がある中で、本当に企業の方々は、苦しい状況の中で競争といいますか、厳しい状況の中で経営を続けられていると思います。そういった中でしっかりと勝ち抜いて、さらに発展をしていくということを考えますと、我々としても、しっかりそこの生産性を向上させていくこと、本当に短期的に今回、経済対策補正もしておりますけれども、そういったことで、限りある財源ではありますけれども、そういったところで必要な補助、支援もしていくという考えも必要でございます。やはりその先にはしっかりと自走していくような、利益を上げながら発展をしていくといった流れにつなげていかなくてはいけませんので、やっぱりそういったことからすると、ただ単に底上げをしていくだけではなくて、県内もしくは県外からの流れということでサプライチェーンをつくっていくということも非常に重要になってくると思います。
なので、そういったことをしながら県民の所得を上げていく、それによって、やはりいろんなものに波及していくことになると思います。消費も増えたり、それによってまた人口、住みよい環境もつくっていけたりとか、そういった好循環になっていくと思いますので、そういった意味ではやはり、昨今の厳しい状況を踏まえて経済対策をしっかりやっていこうということは非常に重要だと、今回、基本的な考え方の1つ目に書かせていただいております。
○記者(長崎新聞社) 所得の向上なり、好循環によってやはり人口減少対策にもつながるという理解でもよろしいでしょうか。
○知事 人口減少対策は、非常にすそ野が広いといいますか、今回、人口減少対策というようなくくりではやっておりません。それは非常に難しい話であって、多分野にわたり、見方によっては人口減少対策になり得るものがほとんどだと思いますので、究極の総合的な、総合的に進めていかなくちゃいけない課題だと思いますから、そういうくくり方はしておりませんけれども、今おっしゃってくださったように、所得という意味では非常に重要な観点だと思いますので、しっかりそういった観点からも経済を回して県民所得を上げていくということは、もちろん人口減少対策だけではありませんけれども、重要な課題の一つだと認識をしています。
○記者(長崎新聞社) それから、その次の重点テーマのことで、個別の施策のことになろうかと思うんですけど、大石県政は子ども施策を柱に据えていて、これまでも出たかと思うんですけれども、知事、この子ども施策の中で、知事肝いりの子ども関連事業というのは、あえて言えばどのあたりになるでしょうか。
○知事 本当いろんな視点があるので、子どもにより視点を当てたところ、子どもが過ごす環境の周りに対する支援とか、本当にいろんな視点があるので、どれとは言いがたいんですが、先ほど取り上げた、長崎県として広域行政として取り組めることというと、やっぱり産後ケアとかですね、それもありますし、あと中間支援組織に関しましては、長崎県で「ココロねっこ運動」が20年来、20年以上続いておりますけれども、そういったネットワークという強みがやっぱりございます。そういったことをしっかり巻き込んでいきながら、県だけではできない取組を、可能な限り多くの方々に参加していただきながら、県みんなで育てようという、この潮流をつくっていくということは非常に重要なことかなというふうに思っております。
○記者(長崎新聞社) それから、子ども施策の中で、ビジョンの新規事業として、こども場所の充実や支援体制ということで新たに基金を創設されるということで、まず、先ほど、財源を確保して弾力的に運用すると、今後何をやっていくかというのは、これからやりながらできることを考えていくのかなと思うんですけれども、もう少し具体的に、このあたりはどのようなイメージがあるのかというのを教えていただきたいんです。
○知事 使途ですか。
○記者(長崎新聞社) 使い方ですね。
○知事 今回、こども場所の運営にかかる支援とか、そういったことを市町、基本的に基礎自治体が担っていくこともあると思いますけれども、そういったところを県としても支援していくこと、今回一緒になってやらせていただくということはありますけれども、そういったことって、今は立ち上げとか初動に対して新しい環境をつくっていこうとしているところだと思いますので、既にあるものに関しましては連携を深めていくとか、コミュニケーションをとっていくとか、また、足りないところは新しいそういう場所、居場所を創出していくとか、もちろん支援はその場その場で、その状況で変わっていくものかもしれませんが、そういったことを維持、発展させていくという意味では、まだまだこれからだというふうに思います。ですので、そういった意味では基金とか、そういったことでしっかりとそれに充てられるような財源をつくっていく、それが重要になると思いますので、これに何年後こういうお金を使いますとか、そういった具体的なものがあるわけではありませんけど、しっかりここが進んでいく方向性として、その財源を確保するという観点では、やっぱりこういったものが必要かなと考えています。
○記者(長崎新聞社) 最後にもう一点。ほかの方からも出ましたけれども、県北振興の中で、IRの不認定を受けて幾つか事業を上げられていますけれども、IRで得た、いわゆるレガシーというものをおっしゃったりしますけれども、それを活かすということよりも、地元の方々は、IRに代わる、それと同じぐらいの対策というのを求められているのかなと思います。そういった意味では今回、イベント事が多くて、先ほどもお話出たように単発で終わるという懸念もあるんですけれども、知事としてはこれで十分と考えているのか、ほかに何かできるようなことがあるのかということを、今どういうふうにお考えになっているのかを教えください。
○知事 これはどれも、県北対策だけではなくて、どの事業もそうですけど、100点満点ではなかなかないものだと思いますし、なので何を言いたいかというと、これだけで十分と思っているわけでは全くありません。ほかの地域でも、やりたいこと、やらなくちゃいけないこと、本当に限りなくある中でではございますけれども、今おっしゃってくださったような単発で終わらないようにということも、視点も大事だと思いますし、実際に実績といいますか、結果が求められていることも十分認識をしております。ですので、県北のIRが不認定に至ったことで、活性化をしていくことについてが大きく形が変わってしまったということは事実なんですけれども、そこは本当にできる限り、その状況に応じてやれることを一緒につくっていくということが、本当にやれることかなと思っています。
ただ、IRに関しましては民間主導の、本当に大型のプロジェクトでございました。これはもう県政の大きなプロジェクトとして進んできたところでございますので、なかなかそれをそのままそっくりと補完するというのは難しさはあると思いながらも、ただ、やはりその中で、先ほどレガシーという言葉を使いわれましたけれども、議論を深めてきた、協力を深めてきたことで生まれたもの、そういったものについては活用しながら、また、足りないものはつくっていきながら、しっかり県北の方々が期待していけるような賑わいづくりといったものは、県としても関係者団体と協力しながら、何とか実現をしていきたいなと、活性化を推進していきたいなと思います。
○記者(長崎新聞社) 分かりました。以上です。
○記者(NHK) よろしくお願いします。今回の当初予算、総括をして、もういろいろ質問が出たので、今回の当初予算を100点満点で評価するなら、総括して何点と評価しますか。理由も一緒にお願いします。
○知事 本当に点数をつけるのは難しいです。やろうと思ったら本当にたくさんやりたいこともありましたし、それも財源の中でもそうですけど、この財源の規模感でよりよい形っていうところは、ほぼほぼ時間のある中で、ほとんどはもう、部局も全力で議論してくれましたし、真剣に向き合っていただいて、キャッチボールも何度もしながら進めてきたところなので、今できることについては、時間的な制限、予算的な財源的な制限がある中でやってきたというふうには思います。
ただ、本当に状況も変われば、求められるものもの変わります。また新たなお話が聞けたり、ニーズが聞けたり、やってみてちょっと違うとかいう意見も出たりとかあると思いますので、それはもう本当に事業を進めていく段階で、過程の中で、できる限り求められたニーズに合うような施行ということをやっていきたいと思っております。
すみません、点数についてはちょっと難しいので、回答は控え・・させていただければと。
○記者(NHK) 今回、周年事業の中で、今年は被爆から80年ということで、それに合わせた予算も3,800万円計上されていますけれども、これについて具体的にどういうことに取り組んでいきたいか、あるいは、それについての思いというのをお願いします。
○知事 被爆80年になりまして、日ごろからいろんな思い、思いは一つですが、いろんな活動をされている方々がいらっしゃいます。そういった方々が、被爆地長崎から世界に向けて発信をする、国内に向けて発信をする、もしくは県内に向けて発信をすることもあると思いますけれど、そういった取組を県としても応援をさせていただきたいと思います。昨年、ノーベル平和賞受賞がありましたけれども、そういった中で機運の高まりを感じていらっしゃる方も多いと思いますし、そういった中で被爆80年ということ、また、被爆者の方々は非常に高齢化している中で、本当に危機感をもってそういったイベントに臨まれ、取組を、続けられている方々もいらっしゃいますので、そういったところをやっぱり被爆80年という節目の年を捉えて、県としても一緒になって応援をしていきたい。核なき平和の実現、長崎を最後の被爆地にという思いをしっかりと伝えられるように取組をしていきたいと思っています。
○記者(日本経済新聞社) よろしくお願いします。一つお伺いします。40ページに、動物殺処分ゼロプロジェクト、3億9,400万円というのがございます。事業の予算というのは、金額の多寡たかというのもかなり重要だと思います。この中でいろいろ出てきて、一番高いのがピース文化祭の7億6,000万円ですが、殺処分は2番目に多いんですね。
知事、これ、何をするんでしょうか。愛護管理センターにかかる経費とか、・・でイメージを教えてください。
○知事 建設にかかることも、整備にかかることもあると思いますので、内訳は、ありますか。
○財政課 財政課からお答えいたします。知事が申しましたように、令和7年度から具体的な動物愛護管理センター、仮称ですけれども、その建設に着手いたしますので、その分が3億6,000万円ほど含まれております。
○記者(日本経済新聞社) 先ほどから皆さんのご質問に知事の思いについてお聞きしているんですが、Xなどで動物殺処分、非常に頻繁に投稿なさっていますけど、その観点から見て、この事業にどういうふうに思い入れがあるか教えてください。
○知事 動物殺処分、私も、就任をして、本当に多くの方々にご協力をいただきながら、ご理解をいただきながら取組を進めてきて、本当に数として減少傾向にあるという状況でございます。私、就任する頃に、すごく数字的には改善が必要だったと認識をしておりますけれども、それは非常にいい方向に向かっているというふうに、実際、現状として感じています。
そういった中で、さらに取組を進めていくという観点もそうですけれども、やはり動物愛護管理センターについてはそれ以上に、触れ合うとか、殺処分だけの対応ではなくて、動物と共生をしていく、そういった役割の場にもなっていくと思うんですね、やっぱり接点として。なので、そういった、ただ殺処分に関する視点だけではなくて、動物と触れあう場所、学ぶ場所、そういった機能もぜひ備えたいと思いますし。
もう一つ申し上げるのは、動物殺処分ゼロの世界観というのを我々目指していますので、そういったときに譲渡数じゃない、収容数というのがやっぱり、この計画をしたときと少し、状況は絶対変わってくると思うんです。そういったときに施設の使われ方というのは、もともとあった数字で機能していただけでは対応しきれない可能性もありますので、そこにやっぱり可変性といいますか拡張性、発展できるような、そんな柔軟性も必要だと、弾力的な運用ができるような施設になっていかなくちゃいけないと思いますので、その観点も大切にしながら、いいものに皆さんとしていければなと思っています。
○記者(日本経済新聞社) 3億6,000万円とかなり大きなお金をかけて造るわけですから、今の段階で、全国でも珍しいとか、こういう特徴があるとか、どういう施設を造りたいか説明してください。
○知事 そうですね、今どういった施設にしたいのかは申し上げたとおりなんですけれども、殺処分ゼロの世界観で言うと、これはまだ達成した先の話になるかもしれませんが、長崎県として、ただゼロで満足するわけではなくて、今、我々長崎県としても他県の方に引き取っていただけたりもしていますので、そういったところで逆に長崎県は、ゼロではなくてマイナスの、逆に受け入れられるような、そういった世界観ももしかしたら見えてくるかもしれませんし、そういった拠点として、さっき言ったように譲渡だけではなくて触れ合うとか学ぶとか、そういった場所、そういった機能を有する、人が集うような、そんな場所にできたらいいなと思っています。
○記者(日本経済新聞社) 他県の殺処分対象の動物を受け入れるというのは、すごい画期的だと思いますので、どうもありがとうございます。以上です。
○記者(朝日新聞社) 教えてください。被爆80年事業についてですけれども、いろんな団体が、活動をしている方々が発信をしていくことを支援するというようなことでお伺いしています。柱としてもそういうことが書いてあるわけですけれども、県として主体的に何か発信をしていくこととかですね。また、80年ということで、いよいよなくなってしまうもの、人のこと、思い、言葉含め、文物もありますけれども、なくなってしまうものもある中で、それを伝えていくために何か県としてやることとか、いろんなことも可能性としてやるべきこと、やれることはあると思うんですけれども、今のところは、団体さんの活動を、発信を支援していくというところに今回の予算では力を入れたということですか。
○知事 イベントとしてですか。
○記者(朝日新聞社) そうですね、予算としては、要するに県が主体的に何かをやるというよりは、やられているところを応援する、一緒になってやるみたいな形でのところを今のところは予算では盛り込まれていると。
○知事 県としては、これまでも次代を担うような人材育成など、そういったことは我々も主体として一緒になってやらせていただいておりますので、そういったところはしっかりと引き続き取り組んでいくことになると思いますし、それに加えて、やっぱり被爆80年、先ほど申し上げたとおり節目でございます。様々な機運の高まりとか、そういったこともありますので、そういった機を捉えてしっかりと、長崎から、また広島とも連携をして、日本からそういった情報発信をしていくといったことを、今年、節目としての捉え方として取り組んでいきたいと考えています。
○記者(朝日新聞社) ありがとうございます。もう1点。これも柱立ての問題ではあるんですけれども、佐世保・県北についてはIRの問題もあり、かなり注目もされ、地域の期待もあるということで取り上げられることが多いですし、力が入った施策、政治姿勢がある施策も出されます。また、離島についても、特殊性もあり、また国境離島新法の話もあるので、そういう中で取り上げられる。
やっぱり気になるのが島原半島の部分について、かなり島原半島の南部とかは、本当に過酷、深刻な状況がどんどん進んでいっていることはもうご承知のとおりだと思います。ここについて多分、一次産業の下支えだとか、周遊だとか、いろんなところで結果的に恩恵は受けるとは思うんですけれども、直接的なところで島原半島ということを意識したような施策というのが、今日の説明の中ではですけれども、直接的な意味ではあまりこう、ちょっと寂しいかなという感じもしたところがあります。
この島原半島について、知事としては、どういうふうに今年度向き合って支えていくかというところ、島原道路の話もありますけれども、どういうふうに整理して向き合っていかれるかというところを教えてください。
○知事 半島ということで、特段、島原だけが抜けているわけでは全くなくて、各地域のこと、思いはもう本当、県内全域に至っていますので、それは触れていないからどうのというわけではありません。ほかの地域も、個別には言いませんけれども、触れていないところもありますが。
全体として施策を考える中で、今おっしゃったように島原半島というのは、非常に一次産業も盛んな場所でございます。加えて、一方でアクセスに課題があるのも事実でございますし、また、医療提供体制という観点からすると、まだ課題も別にあるというふうに認識をしております。ですので、そういった分野、分野ごとの課題といったものも、これはもう島原半島に限ったことではございませんけれども、各地域でしっかり精査しながら、全県下の取組の中でしっかり対応していくということが重要になるかと思います。
島原半島には、本当に強みもたくさんあって、一次産業も、おいしいものもたくさんありますけれども、観光であったりとか、そうですね、たくさんいいものもありますので、そういったことを地域の方々はどう活かしていきたいかということは常に耳を傾けながら、我々県として、広域行政としてやれることをしっかり整理をして取り組んでいきたいと思います。
○記者(朝日新聞社) ありがとうございました。
○記者(西日本新聞社) ちょっと難しい質問にはなるかもしれないんですが、今回の編成された当初予算を一言で表すとするなら、ネーミングをするとするなら、どういうものだというふうに知事自身は思いますか。
○知事 えーと、あの、そうですね、まあ、絆は大切だと思います。いろんな方々、子どもの中間支援もそうですけれども、今お話があった様々な主体をつなげるといったことも非常に重要だと思いますので、私が就任して連携、連携、部局も連携、全て連携、連携と、資源は限られているので、効果を最大化していくという考え方、資源も活用を最大化していく、効果を最大化していくということをしてきましたので、やっぱり「つなげる」ということは非常に重要だと思いますし、今年、県の総合計画を策定しますけれども、その次の総合計画につなげていくということも大切だと思いますので、「つなげる、つなぐ予算」でどうでしょうか。難しい質問でございました。
○記者(西日本新聞社) ありがとうございます。難しいと言われて、出てこないのかなと思ったら、ちゃんと出てきたので、助かりました。ありがとうございます。
○記者(長崎新聞社) 長崎県づくりのビジョンのことでお尋ねしたいんですけれども、知事は、特に前、後ろはないんだというお話を先ほどされていたんですけれども、昨年度は、ビジョンを中心とした政策の紹介の仕方をされていて、特別事業等もありました。で、知事は、その基盤づくりを進めていくんだというようなご説明をされていたと思います。
今回はちょっと、重点項目を掲げたような従来の説明の仕方に戻っていて、ビジョン関連政策は個別の政策に落とし込まれているような紹介の仕方になっているのかなと思うんですけれども、単純に政策のソート相当の手法が異なるだけの話なのかもしれないんですけれども、今回予算編成の中でビジョンがどのような位置づけになっているのか、特に予算でのプライオリティが下がっていますよとか、そういったことではないのかということをちょっとお聞かせいただきたいんですけれども。
○知事 プライオリティが下がったとか、そういったことは全くなくてですね。またむしろ上げたということも全くなくて、やはりどれも大切だという観点は変わりはありません。
それぞれの分野、今回5つのテーマに分けてお示しをさせていただいておりますけれども、その中でビジョン事業ということでご説明をさせていただきました。それぞれの分野が、4つの分野だけでビジョンをですね。昨年は、そのビジョンということもご説明をさしあげて、そのビジョンの中の考え方ということも述べさせていただきながら紹介させていただきましたけれども、今年は、ビジョンだけでもなく、5つのテーマに沿って幅広な、より広い観点からくくり直しをして、その中でビジョンも含めて紹介をさせていただいております。ですので、そういった意味では、恐らく手法による違いといったものが見え方の違いなのかなと思っていますけれども、ビジョンも、基盤づくりというか、一番初めの土台をつくったところから、また次のステップに進んできている段階にありますので、それは全然プライオリティが下がっているというよりも、むしろ次に着々と進めていこうとしている段階にある状況でございます。
また、ビジョンにつきましては、こうありたいと思う、旗印に向かっていくんだと、各事業もこっちを向いていこうねという旗印でもございます。そういった中で、一つの部局だけでは行えないような、むしろ複数の部局にまたがるようなものをみんなで連携して、どういったやり方が一番、限られている資源を有効、最大化できるかということを考えながら議論して進めているものでございますので、むしろこういったものがモデルケースとなって、ほかの事業にも広がっていくといったことで、ビジョンの考え方、部局連携の考え方といったものが広まって、別の個別事業にも広がっていけばいいなと、そうは思っています。
○記者(長崎新聞社) 分かりました。その上でなんですけど、4つ、ビジョンの事業が去年あったと思うんですけど、それぞれに新たな段階があるのかなと思うんですけれども、今のビジョン実現に向けたステップとしてはどういう段階なのかということと、知事の中での進捗状況に関して、ここは進められた、ここはちょっとまだ足りないとか、そういった評価軸があれば教えてください。
○知事 足りないと思うことはもう多々ありますので、それはもう満足ということは全くありませんけれども、それぞれの柱で、やはり我々が財源さえあれば能動的にできるものばかりではありません。例えばドローンでありますとか、そういったところって、特区は指定いただきましたけれども、その枠組みの中で国の実証事業とか、いろんなものを活用させていただいて実現していっていることもあります。また、子どもで言うと、市町だけでなく民間の方々、また、そこの地域にお住いの県民の方々のご理解をいただいて、ご協力をいただいて進むこともあります。
なので、そういったことで県だけでやれるものではありませんので、その都度、その都度、状況に応じてやれることを積み上げて今の形になっていると、そう認識をしています。ですので、足りないということを上げればきりがないとは思いますが、今できることを今回、予算として積み上げさせていただいているということ、その認識でおります。
○広報課長 ほかにご質問はございますか。では、予算の関係については、以上でよろしいでしょうか。
では、ここで終わらせていただきます。