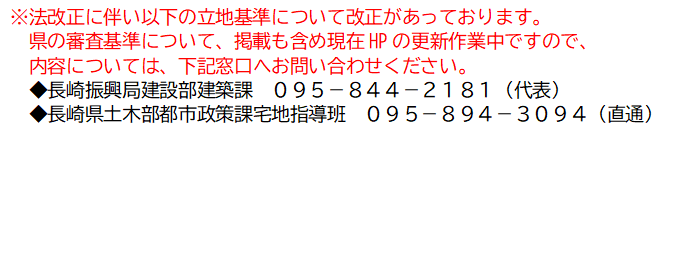改正内容はこちら→→ 安全なまちづくりのための開発許可制度の見直しについて(令和4年4月1日施行)
(法第34条第12号)
本号は、市街化調整区域内で開発審査会の議を経て許可されてきた定型的なもののうち、令で定める基準に従って、県が、区域、目的又は用途を条例で定め、その条例に適合する場合は開発審査会の議を経ずに開発行為及び建築行為が許可対象となる。
なお、長崎県(長崎市及び佐世保市を除く)では、平成17年4月1日から諫早市※、長与町及び時津町の市街化調整区域で運用している。(※現在、諫早市は県の管轄ではありません。)
〇次の要件に適合すること。
1.条例で指定する建築物(住宅)の種類
1)分家住宅
2)土地の収用移転事業により移転される建築物、第1種特定工作物
3)大規模既存集落内の分家住宅
4)大規模既存集落内の自己用住宅
5)公営住宅
6)罹災住宅
2.建築物の種類ごとの規定
1)分家住宅
イ 開発の目的及び申請者の要件について
A 市街化調整区域とされた日前から現在に至るまで当該市街化調整区域内に生活本拠を有する者(本家)の親族が、別世帯を構成する場合に通常必要とされる自己の居住の用に供する住宅のための開発行為であること。
※親族とは、民法第725条に定める親族(血族6親等、配偶者、姻族3親等)
B 申請者は、住宅に困窮している者であること。
ロ 申請に係る敷地について
A 本家が市街化区域内に土地を所有しておらず、または、所有していても住宅の建築が困難な場合で、市街化調整区域となった日より前から当該市街化調整区域内に本家が保有している土地で、その本家から申請者が相続又は贈与を受けたものであること(添付書類としては、贈与証明でも可)。
B 本家が存する既存の集落内又は周辺部の土地であること。
C 申請に係る敷地面積は、500m2以下であること。
D 雨水及び雨水以外の下水を周辺の地域に溢水等による被害が生じないよう、適切な整備がなされていること。なお、下水については、次のいずれかにより排出できること。
a 公共下水道又は農業集落排水事業等により整備された処理施設に接続すること(接続先の管理者等との接続協議が整っているものに限る。)。
b 適切な放流先が確保された合併浄化槽を自ら設置すること(放流先の管理者等と協議が整っているものに限る。)。
ハ 建築物の規模等
A 建ぺい率:60%以下であること。
B 容積率:200%以下であること。
C 建築物の最高高さは原則10mとし、かつ地階を除く階数が3以下であること。
2)土地の収用移転事業により移転される建築物、第1種特定工作物
イ 申請に係る敷地について
A 申請者が自ら所有するか所有となることが明らかであること。
B 敷地面積が500m2以下であること。
C 雨水及び雨水以外の下水を周辺の地域に溢水等による被害が生じないよう、適切な整備がなされていること。なお、下水については、次のいずれかにより排出できること。
a 公共下水道又は農業集落排水事業等により整備された処理施設に接続すること(接続先の管理者等との接続協議が整っているものに限る。)。
b 適切な放流先が確保された合併浄化槽を自ら設置すること(放流先の管理者等と協議が整っているものに限る。)。
ロ 建築物の規模等
A 従前とほぼ同一の用途、規模(従前の1.5倍以下)及び構造であること。
B 建ぺい率:60%以下であること。
C 容積率:200%以下であること。
D 建築物の最高高さは原則10mとし、かつ地階を除く階数が3以下であること。
ハ その他
A 申請者は、住宅(建築物)に困窮している者であること。
B 市街化調整区域への移転がやむを得ない場合であり、当該市街化調整区域における土地の利用と整合するものであること。
3)大規模既存集落内の分家住宅
イ 開発の目的及び申請者等の要件について
A 市街化調整区域とされた日前から、指定既存集落に生活の本拠を有する者の親族が、婚姻等によって別世帯を構成する場合なされる通常必要とされる当該指定既存集落に建築する自己の居住の用に供する住宅のための開発行為であること。
※「指定既存集落」とは、独立して一体的な日常生活圏を構成していると認められる大規模な既存の集落として知事が指定する集落のことである。
B 申請者は、住宅に困窮している者であること。
C 申請者は、市街化調整区域とされた日前から当該指定既存集落に生活の本拠を有する世帯に属する者で、当該指定既存集落に居住又は居住していたことがある者であること。
ロ 申請に係る敷地について
A 申請者が自ら所有するか所有となることが明らかであること。
B 敷地面積が500m2以下であること。
C 雨水及び雨水以外の下水を周辺の地域に溢水等による被害が生じないよう、適切な整備がなされていること。なお、下水については、次のいずれかにより排出できること。
a 公共下水道又は農業集落排水事業等により整備された処理施設に接続すること(接続先の管理者等との接続協議が整っているものに限る。)。
b 適切な放流先が確保された合併浄化槽を自ら設置すること(放流先の管理者等と協議が整っているものに限る。)。
ハ 建築物の規模等
A 建ぺい率:60%以下であること。
B 容積率:200%以下であること。
C 建築物の最高高さは原則10mとし、かつ地階を除く階数が3以下であること。
4)大規模既存集落内の自己用住宅
イ 開発の目的及び申請者等の要件について
A 市街化調整区域とされた日前から、指定既存集落に生活の本拠を有する者当該指定既存集落に建築する自己の居住の用に供する住宅のための開発行為であること。
※「指定既存集落」とは、独立して一体的な日常生活圏を構成していると認められる大規模な既存の集落として知事が指定する集落のことである。
B 申請者は、住宅に困窮している者であること。
C 申請者は、市街化調整区域とされた日前から当該指定既存集落に生活の本拠を有する世帯で出生した者で、当該指定既存集落における居住期間が10年以上である者であること。
ロ 申請に係る敷地について
A 申請者が自ら所有するか所有となることが明らかであること。
B 敷地面積が500m2以下であること。
C 雨水及び雨水以外の下水を周辺の地域に溢水等による被害が生じないよう、適切な整備がなされていること。なお、下水については、次のいずれかにより排出できること。
a 公共下水道又は農業集落排水事業等により整備された処理施設に接続すること(接続先の管理者等との接続協議が整っているものに限る。)。
b 適切な放流先が確保された合併浄化槽を自ら設置すること(放流先の管理者等と協議が整っているものに限る。)。
ハ 建築物の規模等
A 建ぺい率:60%以下であること。
B 容積率:200%以下であること。
C 建築物の最高高さは原則10mとし、かつ地階を除く階数が3以下であること。
5)公営住宅
イ 申請に係る敷地について
A 申請者が自ら所有するか所有となることが明らかであること。
B 敷地面積は、適切な規模であること。
C 雨水及び雨水以外の下水を周辺の地域に溢水等による被害が生じないよう、適切な整備がなされていること。なお、下水については、次のいずれかにより排出できること。
a 公共下水道又は農業集落排水事業等により整備された処理施設に接続すること(接続先の管理者等との接続協議が整っているものに限る。)。
b 適切な放流先が確保された合併浄化槽を自ら設置すること(放流先の管理者等と協議が整っているものに限る。)。
ロ 建築物の規模等
A 建ぺい率:60%以下であること。
B 容積率:200%以下であること。
C 建築物の最高高さは原則10mとし、かつ地階を除く階数が3以下であること。
ハ その他
A 当該指定既存集落内において、主として当該指定既存集落及びその周辺部に居住するものを入居の対象として建設されるものであり、その規模がその地域の入居対象者を勘案して適切であること。
6)罹災住宅
イ 開発の目的及び申請者等の要件について
A 災害があった場合、市町長の発行する全壊又は流出の罹災証明書の交付を受けた者が、災害のあった日からおおむね5年以内に、建築する従前とほぼ同一規模(従前の1.5倍以内)の自己の居住の用に供する住宅のための開発行為であること。
B 申請者は、住宅に困窮している者であること。
ロ 申請に係る敷地について
A 申請者が自ら所有するか所有となることが明らかであること。
B 敷地面積が500m2以下であること。
C 雨水及び雨水以外の下水を周辺の地域に溢水等による被害が生じないよう、適切な整備がなされていること。なお、下水については、次のいずれかにより排出できること。
a 公共下水道又は農業集落排水事業等により整備された処理施設に接続すること(接続先の管理者等との接続協議が整っているものに限る。)。
b 適切な放流先が確保された合併浄化槽を自ら設置すること(放流先の管理者等と協議が整っているものに限る。)。
ハ 建築物の規模等
A 建築基準法別表第2(い)項、第1号及び第2号に該当するものであること。
B 建ぺい率:60%以下であること。
C 容積率:200%以下であること。
D 建築物の最高高さは原則10mとし、かつ地階を除く階数が3以下であること。
3.条例で指定する区域
1) 次の区域を含まないこと。
イ 原則として、溢水、湛水、津波、高潮等による災害の発生のおそれのある土地の区域。
ロ 優良な集団農地その他長期にわたり農用地として保存すべき土地の区域。
ハ 優れた自然の風景を維持し、都市の環境を保持し、水源を涵養し、土砂の流出を防備する等のため保全すべき土地の区域。
| 法第34条(開発許可の基準)
十二 開発区域の周辺における市街化を促進するおそれがないと認められ、かつ、市街化区域内において行うことが困難又は著しく不適当と認められる開発行為として、令で定める基準に従い、都道府県の条例で区域、目的又は予定建築物等の用途を限り定められたもの |
| 令第29条の7(開発許可をすることができる開発行為を条例で定める場合の基準)
法第34条第12号(法第35条の2第4項において準用する場合を含む。)の令で定める基準は、同号の条例で定める区域に、原則として、第8条第1項第2号ロからニまでに掲げる土地の区域を含まないこととする。 |
| 条例第5条(法第34条第12号の条例で定める開発行為の区域等)
法第34条第12号の規定により条例で定める開発行為は、市街化調整区域のうち、政令第8条第1項第2号ロからニまでに掲げる土地の区域以外の区域で行う開発行為であって、次に掲げるものとする。 |
| (参考) 令第8条 二 |
このページの掲載元
- 建築課
- 郵便番号 850-8570
長崎県長崎市尾上町3番1号 - 電話番号 095-894-3091
- ファックス番号 095-827-3367